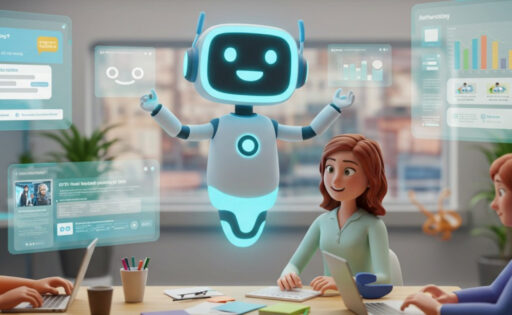“監視カメラ作動中”の張り紙に学ぶ──AI時代の「設計力」とは何か?
たった一枚の張り紙から見えた“設計の本質”
こんにちは。人の見てないところでも良いことをして善徳を積みつつ、密かにリターンを求めてしまうために自分のしたことを聞かれていもいないのアピールする男、株式会社セレンデック代表の楠本です。先日、駅前の商店街を歩いていた時のことです。
ある飲食店の前に、業務用らしき大きなバケツが置かれていました。
その蓋の上に、ひとつの張り紙。
「監視カメラ作動中」
ああ、なるほど。
この店、いろいろ試行錯誤してきたんだろうな──そんなふうに、私は勝手に背景を想像していました。
おそらく、最初は「関係者以外ゴミ捨て禁止」などの注意書きをしていたはずです。
でも、残念ながら世の中には“そんなの関係ねぇ”という人たちも一定数存在します。ええ、小島よしおさんではありませんが(笑)。
そうした背景から、この店は「モラルに頼る訴求」ではなく、「抑止力としての心理設計」に切り替えたのでしょう。
注意書きよりも、“見られている”という感覚のほうが、人の行動に効く。
このたった一枚の張り紙に、設計者の“現場視点のリアリティ”を感じずにはいられませんでした。
AI時代の新常識:設計思考がWebライティングを変える
ユーザーの行動を促す心理学の力
心理学では「プロスペクト理論」という有名な考え方があります。
人は「得をする」よりも、「損を避ける」ことに強く反応する
まさにあの張り紙がそうです。
「ゴミを捨てないで」よりも「見られてるよ」というメッセージの方が、捨てることの“リスク”を想起させ、無言の抑制につながる。
マーケティングやコピーライティングでもまったく同じです。
「このサプリで痩せます」よりも「今のままだと、太りやすい体質のままです」
この違いだけで、反応率が大きく変わります。
AIを使いこなすための「問いの設計」とは
最近では、ChatGPTなどでコピーを自動生成する流れも増えています。
でも、ここで大事なのは「何を聞くか」です。私自身、こんな実験をしました。
Q1:「キャッチコピーを考えて」
Q2:「人間心理に基づいた、損失回避を活かしたキャッチコピーを考えて」
すると、出てくる答えがまったく違うんです。
前者は無難で汎用的な表現、後者はしっかりと“心理設計”が組み込まれた言葉に。
つまり、AIの出力は“問いの精度”に比例するということ。
AIを「思考のパートナー」にする方法
よく、「AIってすごいですね」と言われます。
でも、本質は違います。
AIは“すごい答え”を持っているのではなく、“すごい問い”に応えてくれる存在です。
だからこそ、「どう聞くか」「どの文脈で聞くか」が大事なんです。
その部分を雑に扱うと、出てくるのは“それっぽいけど刺さらない”言葉ばかり。
これはコピーもUXも同じ。結局、設計力で勝負は決まります。
読者の心を掴むコンテンツ設計:7つのチェックリスト
以下のポイントは、私がChatGPTに“うまく聞いたとき”に導き出されたものでもあります。
AIを使うにせよ、自分で書くにせよ──「読者が立ち止まる構造」を意識したいところです。
📌設計のチェックリスト(箇条書き)
- 数字と具体性:例「97%が改善を実感」「5日間で体感」など
- ネガティブの逆手取り:「今のままだと損をします」など
- 違和感と意外性:「監視カメラ作動中」など見慣れない要素で注意を引く
- 共感の導線:「あ、それ私のことだ」感を演出する言葉
- ストーリー性:ビフォーアフターや体験談を組み込む
- リズムと音読感:声に出したときに気持ちいいリズムがあるか
- 信頼性の体験提示:実際の声・数字・エビデンスがあるか
このチェックリストを意識することで、読者の注意を引きつけ、最後まで読み進めてもらうための基盤を築くことができます。AIを活用する場合でも、これらの要素を「問い」に組み込むことで、より質の高いコンテンツが生成されるでしょう。単なる情報の羅列ではなく、読者の感情や行動に訴えかける「設計」こそが、AI時代のコンテンツ作成に求められるスキルです。
AIは「ツール」ではなく「ビジネスパートナー」
AIを有効活用するための思考法
AIは万能ではありません。
でも、適切なコンセプトやターゲット、意図を提示すると、私たちが思いつかない角度の案をどんどん返してくれます。「問いを設計する」という仕事は、人間側の責任なんですね。
「AIに何を質問するか」が成果を決める
現場でよくある失敗例は、「AIに全部考えさせようとして、方向性がブレてしまう」ケースです。
でも、AIは“問いを深める相手”と捉えると、その真価を発揮します。
- どんな人に届けたいか?
- どんな誤解を防ぎたいか?
- どんな行動を引き出したいか?
このような“設計思考”を深める相手として、AIはとても頼れるパートナーです。
まとめ:AI時代に必須の「問いの設計」スキル
「AIに何を聞くか」が、そのまま「あなたが何を考えているか」を映し出す鏡になる
AI時代のクリエイティブとは、発想ではなく設計に宿るのかもしれません。
言い換えれば、“人間の問い”が深くなるほど、AIの出力も“自分ごと化”してくる。
そんなふうに感じた、駅前のゴミバケツとの出会いでした(笑)。
よくある質問
- Q1:AIでコピーって本当に効果あるんですか?
A:設計さえ丁寧に行えば、十分に反応率の高いコピーが作れます。ただし“丸投げ”ではなく、“共創”が鍵です。 - Q2:うちの業種はニッチすぎてAIには無理じゃ?
A:むしろニッチなほど、深い問いやペルソナ設計が明確になれば、AIの力を引き出せます。 - Q3:設計ってどうやって学べばいいんですか?
A:まずは「誰に何を伝えたいか?」を明文化するところから。セレンデックではその伴走も行っています。 - Q4:AIの回答が浅くてがっかりした経験がある…
A:原因の多くは“問いの浅さ”です。文脈や目的を添えて再質問すると、ぐっと精度が上がります。 - Q5:どこまでAIに任せて、どこから人間がやるべき?
A:「設計=人」「出力=AI」と考えるのが基本です。ただし、フィードバック・修正は必ず人間が行う必要があります。 - Q6:今すぐAI活用に取り組むべきか迷ってます…
A:すぐ取り組む必要はありません。ただし“設計思考”はAI時代の基本リテラシー。小さな実験から始めるのがおすすめです。
セレンデックのWebディレクション講座で「設計力」を磨く
- 個人向け:AI時代の“考える力”を育てる
『AI Webディレクター養成講座』- ChatGPTやGeminiなどを活用した、ゼロから始めるAI仕事術
- Webの基本技術、ヒアリング・構成・提案・ライティング・AI活用の“ディレクション5技能”を実務に落とし込む
- Web初心者・未経験者でも、「考える力」と「伝える力」を体系的に学べる講座です。0からAIwebディレクターとして活躍できるまでをサポートします
- 法人向け:AI導入から内製化までを設計
『AI・DX戦略構築講座(法人研修プラン)』- 現場で「なぜ進まないのか」を構造的に分析
- 部署別ヒアリングから始める“内製化の第一歩”
- 最新AIツールの活用例と、現場に定着させる教育設計をワーク形式で支援
「気づき」って、いつも静かに、そして突然に訪れるものです。
この出会いが、誰かの設計力のヒントになれば嬉しいです。 AI時代、一緒に頑張っていきましょう!
上記の講座に限らず、何でも構いませんのでお気軽にご連絡、ご相談ください。
株式会社セレンデック代表 楠本