構成もAIでOK”の時代に──Webディレクターが“選ばれ続ける”ための7つの進化とは?
そんなモヤモヤ、感じていませんか?
こんにちは。AIツールに課金して何でも試してみたい、AI企業からすると”カモ”なAIユーザー、AIウェブディレクターの楠本です。株式会社セレンデックで代表をしております。
AIが登場して以来、Webディレクターという職種がじわじわと──しかし確実に変化を迫られています。
現場では今、何が起きているのか?
そしてこれから、どんなスキルが求められるのか?
本記事では「スキル変化」にフォーカスし、AI時代に“生き残るディレクター”に求められる進化をリアルに掘り下げていきます。
…というとちょっと仰々しいですが、現場であったホンネと試行錯誤を、なるべくリアルに書きますね。
「構成を考える」がAIで済む時代──そのとき人は何をする?
ある日、ChatGPTに「ペルソナは30代女性、目的は育児と仕事の両立。これに合うLP構成を3つ出して」と打ち込んでみました。
結果──5秒後には「あり得る構成」が3パターン並んでいたんです。
「いや、早すぎるやろ(笑)」と、思わず画面にツッコミました。
もちろん、そのまま使うわけではない。でも「案出しにかかっていた1時間」が、瞬時に短縮された衝撃。
これは、Webディレクターの“仕事の本質”を問う出来事でした。
「考える」こと自体は、もはやAIもできてしまう。じゃあ人間の価値って、どこにあるのか?
それを突きつけられたのです。
変わったのは「何を考えるか」より「どこで価値を出すか」
AIが構成・コピー・ワイヤーフレームを生み出す中で、ディレクターの役割は「出す」から「選ぶ・翻訳する・判断する」にシフトしています。
たとえば、AIが提示した3つの構成案──それを「どう選ぶか」「なぜそう判断するか」を説明できる人が、チームの羅針盤になります。
「選べない」「良し悪しを判断できない」ディレクターは、もはや“ボトルネック”になりかねません。
私自身も、初期は迷いながらも「これは何のため?」「どの構成が最もユーザーの感情に寄り添っているか?」を自問し続けることで、判断の軸が磨かれていきました。
逆に言えば、これは“人間にしかできない仕事”だと気づいた瞬間でもありました。
そして、もう一つ大事な視点があります。
それは──「責任を取れるか」です。
AIは案を出せても、選択の責任を負うことはできません。成果が出た、出なかった。炎上した、しなかった。
その全責任は、意思決定をした“人間”にしか背負えない。
Webディレクターとは、「意味を見出し、選び、責任を持つ」仕事になったのだと、私は思っています。
だから正直、「気楽にプロンプト打って、あとはAIに任せよう」では済まない。
むしろ、AIが案を出す分、ディレクターの“責任の重み”は増しています。
ここに面白さもありますけどね(笑)
実際、制作現場では「FigmaとAI連携でバナーが10分でできた」と驚かれることも増えました。速さはすごい。でもそのデザインに“どんな意図があるのか?”は、やっぱり人が答えるしかないんです。
ある若手メンバーが「構成案は任せてください!」と意気込んでAIから出力してくれたのですが、その構成をお客様に見せる前に「これ、なんでこの順番なん?」と聞いたらフリーズしてしまった(笑)
つまり、“選ぶ”と“意味づける”の間には、意外と大きな壁がある。
そして、その壁を越えるのが「これからのディレクターの役割」なんですよね。
今、Webディレクターに求められる“7つの進化”
以下は、私自身が現場で痛感してきた「生き残るためのスキル進化」です。
1. ファシリテーション力
AI×人間の混合チームにおいて、今や「自分の意見」だけでは不十分です。
必要なのは、“みんなが納得する意思決定”を導ける力。
意見の衝突や曖昧な要望を咀嚼し、翻訳し、まとめていく──そんな「場を整える力」が、これからのディレクターには必須になります。
2. AIリテラシー
「AIは得意な人に任せよう」と思っていませんか?
でも、AIの出力を正しく“評価”するには、自ら使い倒してみるしかないんです。
ChatGPT、Notion AI、Midjourney…少し触るだけでも、発想の幅がガラッと変わります。まずは、自分の手で触って確かめてみてください。
3. 意思決定力
AIが複数の案を提示してくれる時代、「どれを選ぶか」が、ディレクターの仕事になりました。
ただ“良さそう”ではなく、「なぜそれを選んだか」を言語化し、チームやクライアントを説得する力が求められます。
迷って止まるより、「決めて動かす」ことが、今の現場では一番の価値なんですよね。
4. 翻訳力
抽象的なオーダーやAIの出力を、“人に伝わる言葉”に変える。
「いい感じで」「女性向けに」「ちょっとポップな」──そんな曖昧な依頼も、ディレクターが噛み砕き、形にしないと前に進みません。
クリエイティブと言語の間をつなぐ“翻訳者”としての力、今後ますます問われていきます。
5. 仮説構築力
「この構成でユーザーは反応するか?」
「この見出しは、本当に刺さるのか?」
すべてが不確実な中で、“たぶんこれが効く”を設定し、素早く試す。その仮説と検証のサイクルをどれだけ早く回せるかが、成果を左右します。
ロジックだけでも直感だけでも足りない。両方を磨いていく必要があります。
6. ストーリーテリング
構成を“ただ並べる”だけでは、もう届きません。
読み手の感情の流れ──驚き、共感、不安、納得──を設計しながら、構成やコピーを組み立てていく。
これは、AIにはまだ難しい。“人の気持ち”がわかるディレクターにしかできない仕事です。
7. 問いを持つ力
「これって、本当に必要?」
「効率化のために、意味が薄れてないか?」
AIが答えを出してくれる今だからこそ、“問い直す”ことが、ディレクターの大切な仕事になります。
便利さに流されすぎず、“意味”を問い直す姿勢が、結果としてクオリティに直結します。
変化を受け入れた先に、チャンスがある
最初は戸惑うと思います。実際、私も「こんなに変わるの!?」と呆然とした時期がありました。
でも──その変化の先には、可能性があります。
AIに奪われるのではなく、AIを使いこなす側に回ったとき。Webディレクターという仕事は、より意味のある役割へと進化するはずです。
これは、単なる“効率化”ではありません。
「人がやるべき仕事」に、より多くの時間とエネルギーを使えるようになる。
それが、AI時代のディレクションにおける“本当のチャンス”だと感じています。
まとめ:あなたは、どの進化に着手しますか?
全部をいきなり習得する必要はありません。
まずはひとつ、「これならできそう」というスキルから。
たとえば、ChatGPTで「構成案3つ出して」と打ってみる。
たったそれだけで、自分の“判断力”が問われるフェーズに入ります。
やってみて、迷って、また考えて。
その繰り返しの中に、“これからのあなたらしいディレクター像”が見えてくるはずです。
AIの進化は止まりません。過去にしがみつかずに、このさい変化の波に乗りましょう!
👉 AIを活用してWebディレクション能力を高めたい、学びたいかたは「AIディレクター養成講座」をご検討ください。説明会も行っています
よくあるご質問(FAQ)
Q1. そもそも、AIってディレクターにどこまで必要?
A. 必須ではありません。ただ「使える」と「使いこなせる」には大きな差があります。
Q2. 構成やコピーをAIがやってくれるなら、ディレクターって必要ですか?
A. むしろ「選ぶ」「意図を説明する」ことの価値が上がってきています。
Q3. いきなり全部やるのは無理そう…
A. 大丈夫です。記事内にもあるように、まずは「ひとつのスキル」からでOKです。
Q4. ChatGPTって、どこまで信用できますか?
A. あくまで“提案ツール”と捉えてください。判断は人間の仕事です。
Q5. 「AIを使う自信がない」場合はどうすれば?
A. 実際に使ってみることが一番の近道です。失敗しながら学べばOKです。
次のステップへ:もっと学びたい方へ
セレンデックではAIウェブディレクター育成講座を開催しています。ご興味ある方は是非ご参加ください。体験会、説明会も実施しています。










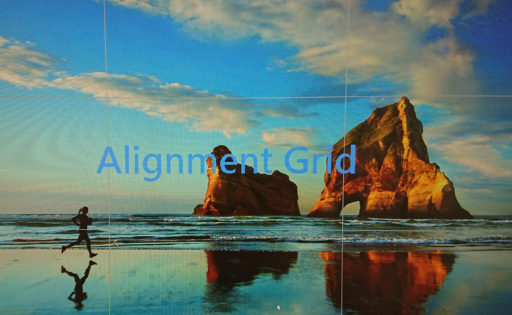





「最近、構成案をAIに任せることが増えてきた…」
「案出しが秒で終わるのはすごいけど、なんか自分の出番が減った気がする」
「これって便利だけど──自分、何をすればいいんだっけ?」