解説YouTube動画はこちら 中小企業はAIをどう使うべきか|社長が知らないと“確実に損する”AI活用の現実
“AI以前”で止まる現場…それ、よくある話です
こんにちは。手書きメモをもらうと、ちょっとほっこりする男、株式会社セレンデック代表の楠本です。
最近、「AI導入したいけど現場がついてこなくて…」という相談が本当に増えています。
でも、それって当然なんです。
実際にお客様の現場に足を運んでみると──
「まだFAXなんです」とか、「クラウドって何?」という声が、ザラにあるんですよ。
正直、AIどころかまずITの基本からなんとかせなアカン…みたいな(笑)
でも、これを「遅れてる」と切り捨てるのは違うと思っていて。
30年前にはそれが“最適解”だったんですよね。
ただ、環境が変わった今、その“最適”を見直すタイミングが来てるんです。
そういう意味でも、AIを入れるって単なるテクノロジーの話じゃないんですよ。
社内文化や価値観のアップデートでもあるわけです。
AI導入を成功させるための全体像を知りたい方は、
AI導入を成功させるための5つの戦略的ステップもあわせてお読みください。
なぜ今、AIリテラシーの底上げが必須なのか?
AIリテラシーって言葉、ちょっと構えちゃいますよね。
でも要は、「AIってなんなん?」をちゃんと理解して、自分の業務にどう役立つかを判断できる力のこと。
これ、別に専門家になれって話じゃなくて──
- 何が得意で何が苦手か
- どこまで任せて、どこは人がやるべきか
- リスクや落とし穴はどこか
このへんが分かるだけで、仕事の進め方がガラッと変わるんです。
AIが何でもできる魔法の杖だと思っていると、逆に現場の信頼を失います。
「結局、人間が調整するんでしょ?」「むしろ余計に時間かかるんじゃ…?」
そんな不信感を生まないためにも、まず“正しく理解する”ことが第一歩なんですよね。
特に中小企業では、「どうせAIなんてウチには関係ない」と思われがちですが…実はそういう会社ほど、リテラシーがカギを握ります。
戦略的AI導入のステップ──社内展開を見据えた設計
「とりあえずAI使ってみよう!」じゃ、たいてい失敗します。
導入しても「なんかめんどくさい」「よく分からん」で放置されるケース、多いんですよ。
だからこそ、私は次の5つを意識しています:
- 経営層と現場の連携
- 目的の明確化(Why)
- スモールスタート(POC)
- 最適なツール・パートナー選定
- 継続的な改善と効果測定
この辺の詳細は親記事に譲りますが、今回の記事では特に“現場の育成と空気づくり”に焦点を当てます。
“現場の痛み”を無視しない設計にする
AIって、便利そうに見えて、導入の仕方を間違えると「現場の手間が増えただけ」ってなりがちです。
現場にとっての「納得感」がなければ、どんなに高機能なツールも意味がない。
たとえば──
これ、あるあるです(笑)
でも、よくよくヒアリングすると、修正箇所って2〜3割程度だった。
つまり、「最初から“修正込み”で設計する」ことと、「それでも7割ラクになる」と伝えることで、見え方がガラッと変わるんですよね。
“完璧な成果”を目指すとAI導入は空回りします。
“ある程度の下地をAIが作る”という使い方に切り替えると、一気に現場の納得度が上がる──これ、かなりの気づきでした。
つまり、ツール選び以上に、「使い方の設計」と「使う人の納得感設計」が肝なんです。
AIリテラシー育成のステップとおすすめ施策
ステップ1:ITリテラシーの底上げ
正直なところ、私自身はWeb制作を生業にしてきたので、ITそのものに苦手意識はありませんでした。
ただ、それでも社内でAIやクラウド活用を本格的に進めようとしたとき──「あれ?意外とここ説明が必要かも…」と思う場面が増えたんです。
たとえば、Google Workspaceの共有設定やチャットワークでの通知ルール、Google Meetの録画設定など、日常的に使っているツールでも「ちゃんと教えたことなかったな」と気づかされました。
つまり“ITが得意”な人が多い会社でも、「全社的に底上げする」には設計が必要なんです。
最近では、「パソコン教室 in 社内」みたいなライトな勉強会を取り入れる会社さんも増えてますが、重要なのは単なるツール説明ではなく、
- どこでつまずきやすいか?
- どんな風に伝えると響くか?
- 誰が“先生役”になると安心感が出るか?
といった“場の設計”にあります。
大事なのは、「こんな質問してもいいのかな?」を払拭する空気感。
ツール以前に、聞ける環境づくりが何よりも大切です。
ステップ2:AIの基本知識・使い方の学習
ChatGPTやNotion AIなど、触ってみるのが一番早いです。
「プロンプト設計」──つまりAIに“どう頼むか”って技術。
これが実は、業務効率に直結するんです。
「こんな依頼、AIにできるの?」という疑問も、実際に試してみると「あ、これ使えるじゃん!」って発見があります。
ステップ3:小さな業務改善から着手
Googleフォーム+スプレッドシートで、社内申請を自動化──これだけで「紙に書いてハンコ押してた時代って何?」になります。
まずは目に見えてラクになるところから。これが鉄則です。
ステップ4:成果の共有とナレッジ化
「うまくいった」「やってみたけど失敗した」──どっちも財産です。
Slackのチャンネルで事例共有したり、月1でLT(ライトニングトーク)をやるだけでも、雰囲気は変わります。
“失敗談”ほど、他部署にとって役立つリアルな知見になったりします。
導入ハードルを下げる“工夫”と“空気づくり”
私のオススメは、最初から完璧を目指さないこと。
「失敗OK」「分からなくて当たり前」な文化づくりこそが、リテラシーを育てる最大の支援になります。
たとえば──
- 「今日のわからん報告会」
- 「先生役を持ち回りにする勉強会」
- 「AIじゃなくて“あい”でサポートするチーム(笑)」
こんな感じで、ちょっとユーモア混じりにやると、スッと入りやすくなります。
ツール導入より先に、“空気のインストール”をやっておく。
これが意外と効きます。
まとめ:AIリテラシーは、会社の未来を左右する“土台”になる
AI導入って、“どこのツール使うか”より、“誰がどう使うか”のほうが100倍大事なんですよね。
だからこそ、現場の育成が肝になる。
焦らず、でも確実に“使える組織”へ進化していく──その一歩を、今日から始めませんか?
この気づきが、どなたかの現場にとっての“変化の種”になればうれしいです。
よくある質問(FAQ)
- Q1. AI導入を検討していますが、何から始めればいいですか?
A. まずは、社内で最も手間のかかっている業務や、改善したい課題を洗い出すことから始めましょう。具体的な「痛み」が分かれば、AIを導入する目的も明確になります。その上で、小さな課題を解決できるAIツールをスモールスタートで試してみることをお勧めします。 - Q2. AI導入には高額な費用がかかりますか?
A. 確かに、大規模なシステム開発には費用がかかりますが、無料で使えるAIツールや、低コストで始められるSaaS型ツールも多数あります。まずは、無料プランやトライアル期間を活用して、自社の業務に合うか試してみるのが良いでしょう。 - Q3. AIの知識がなくても、使いこなせますか?
A. はい、問題ありません。最近のAIツールは、専門知識がなくても直感的に使えるものが増えています。重要なのは、AIの「得意なこと」と「苦手なこと」を理解すること。そして、社内で気軽に質問・相談できる「空気づくり」をしておくことです。
- 個人向け:AI時代の“考える力”を育てる
『AI Webディレクター養成講座』- ChatGPTやGeminiなどを活用した、ゼロから始めるAI仕事術
- Webの基本技術、ヒアリング・構成・提案・ライティング・AI活用の“ディレクション5技能”を実務に落とし込む
- Web初心者・未経験者でも、「考える力」と「伝える力」を体系的に学べる講座です。0からAIwebディレクターとして活躍できるまでをサポートします
- 法人向け:AI導入から内製化までを設計
『AI・DX戦略構築講座(法人研修プラン)』- 現場で「なぜ進まないのか」を構造的に分析
- 部署別ヒアリングから始める“内製化の第一歩”
- 最新AIツールの活用例と、現場に定着させる教育設計をワーク形式で支援
AI導入の次の一歩を考える
「うちでもAI、始められるのかな…?」
そんな不安や疑問があれば、ぜひ一度ご相談ください。
現場の温度感に合わせた、無理のない一歩をご一緒に考えましょう。ここまで読んでくれてありがとうございます。AI時代、一緒に頑張っていきましょう!!









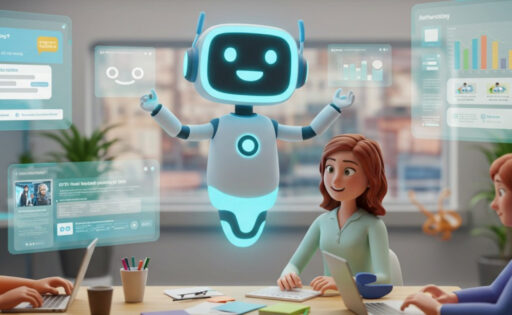






毎月の報告書を、手書き→PDF化→手入力…という三段活用でやっていたお客様がいらっしゃいました。そこでAIを使って要約・整理を自動化したんですが、現場からは「結局、あとで直すから意味ないんじゃ?」という反応が返ってきたんです。