1. 「あ、それ最初に言ってよ…」──現場でよくある“伝え方ミス”の正体
こんにちは。関西出身ではないですが文章だけでエセ関西弁を目指す、株式会社セレンデック代表の楠本です。
「これどう思いますか?」「あー、それならこうすれば…」「いや実は○○で…」
──この会話、あなたの職場でもよくあるやり取りではないでしょうか。
正直、私は何度もあります。部下との相談、クライアントとのやりとり、日々の社内ミーティング…
いわゆる“情報の後出し”により、せっかく真剣に考えた提案がまるっと無駄になる──そんな経験、少なくありません。
「最初に言うてや~」。え、それ最初に言ってくれれば…ってやつですね(笑)
最初から背景を共有してもらえていれば、こちらも的確な助言ができたはずなのに。
それができなかっただけで、思考コストも時間も信頼も失ってしまうんです。
このような「伝え方のズレ」は、ちょっとした意識で減らせます。そして、それができるだけで、驚くほど仕事がスムーズになる。AI時代の今だからこそ、改めて「質問力」という“見えないスキル”が問われていると感じます。
2. “伝えていない”ことが、相手の時間と信頼を奪っている
断片的な質問がもたらす3つの弊害
- 思考の無駄:回答者が前提の誤解に基づいて考えてしまう
- 時間のロス:後から補足→再思考という二度手間が発生
- 信頼の低下:相手に「情報を小出しにされた」という不信感を与える
私自身、日々のやり取りで感じるのですが、こうした“伝え漏れ”による摩擦は、意外にも社内外問わず起きています。上司・部下・クライアント──関係性にかかわらず、情報の粒度が違うだけで、結果はまったく変わってしまうんですよね。これ、経験ある方多いと思うんですが──どうでしょう?
伝え方に足りない5つの要素
- 目的:なぜこの質問をしているのか?
- 背景:どんな状況で発生した問題か?
- 前提条件:すでに決まっていること/避けたいことは?
- 選択肢:どのような案が検討されているか?
- 思考の経緯:なぜその選択肢に至ったのか?
この5つを意識するだけで、質問の質が劇的に変わります。要は「脳内で考えていることを、どう構造化して伝えるか」。そのひと手間が、相手の理解と反応スピードを一気に変えるんです。
3. “質問設計”をするだけで、すべてが変わる
まずは「これは相談?報告?質問?」の確認から
これは本当に小さなことですが、実はとても大きな差になります。
会話の冒頭に「ちょっと相談なんですが」か「これ、報告です」なのかを明言するだけでも、相手の脳内準備が変わります。何を求められているのかが分からないと、相手は“最適なモード”に切り替えられない。これは、非常にもったいないことです。
構造化された質問フォーマット
以下のようなテンプレートを使えば、相手が理解しやすく、AIにも伝わる構造になります:
- 【目的】:何を決めたい/解決したいか?
- 【背景】:何が起きているか、何がトリガーか?
- 【前提条件】:制約条件・既知の事実など
- 【選択肢】:A案、B案、その他の方向性
- 【考察】:今のところどう考えているか
このテンプレート、実は社内の報告資料やクライアント提案書でもそのまま応用可能です。
「伝える力」は「思考整理の力」でもある。質問力は、コミュニケーションスキルではなく“仕事力”そのものなのだと、私は実感しています。
4. 現場の知恵|できる営業マンがやっている「ヒアリング設計」
家電営業に学ぶ“質問の逆算”
優秀な営業マンは「何を売るか」ではなく「誰に、どのように使われるか」を起点に質問を組み立てます。
例えば掃除機を売るとき、「どれがいいですか?」とは聞きません。
- 「ご家族は?何人で住んでます?掃除するのはフローリングですか?ペットはいますか?」
──そうやって、“最適な提案の判断基準”を引き出していくんです。これは単なる営業トークではなく、ヒアリング設計の力です。
Webサイトではなくチラシを薦めた理由
あるクライアントが「Webサイトを作りたい」と来られた際、ヒアリングを重ねるうちに「それ、チラシで良くないですか?」と提案しました。
予算も用途も、紙の方が合理的だったからです。
このような判断は、売りたいものを売るのではなく、「本当に役立つ提案をする」という視点があってこそです。だからこそ、“質問設計力”が問われるんです。
5. 応用編|AIと向き合う力=自分の考えを整理する力
プロンプトとは“構造化された相談書”である
AI(特にChatGPT)も、人と同じで「聞かれた内容」に沿ってしか答えられません。
背景や目的が抜けたままでは、曖昧な返答しか返ってこない。
例:
回答はぼんやり
「採用強化のためのコンテンツ戦略を立てたい。今の流入が弱いのはここ。ターゲットは○○層」 → 的確な提案が返る
AIにうまく働いてもらうには、自分の考えの整理=プロンプト設計が不可欠です。
AIは「優秀な営業マン」として進化している
最近のAIは、情報が足りなければ聞き返してくることもあります。とはいえ、その「最初の問い」がボヤけていると、それもままなりません。
こちらの構造力次第で、AIが「雑談相手」にも「戦略パートナー」にもなってくれる。
まさにAI時代の分かれ道だと思っています。
6. 成果と気づき|「質問の質」は信頼も成果も左右する“見えないスキル”
質問が上手い人は、提案も速く、信頼も厚い
実感として、「質問がうまい人」は、全体の進行やコミュニケーションでも一歩リードしています。
自分の中の“迷い”をそのまま投げるのではなく、整理して「こう考えてますがどうでしょうか?」と伝えられる人。相手も一緒に考えやすくなり、「この人とはスムーズに仕事ができるな」と自然に思ってもらえるんです。
中高年の“経験”こそ、AI活用の最大資産
豊富な現場経験を積んだ中高年層こそ、AI時代に“言語化の力”を持っている。
経験をプロンプトに変換できれば、それ自体が強力な資産になります。
👉 関連リンク:経験格差をチカラに変える、中高年のためのAI活用法
7. まとめ|質問とは「相手への敬意」であり、最高の効率化手段
- 曖昧な質問は時間の浪費とストレスを生む
- 構造化された伝え方は、信頼と成果を生む
- AI時代だからこそ、「何をどう伝えるか」が問われている
その一言が、相手の思考を大きく変えるかもしれません。
質問とは「問いかけ」ではなく「提案」でもある──そんな感覚で向き合えると、仕事もAI活用も一段深まっていきます。あなたの質問、“伝わる設計”になっていますか?
8. FAQ|質問・相談・プロンプトにまつわる誤解と解消
- Q1:そもそも背景とか選択肢なんて整理できません…
A:完璧に整理しなくてOKです。「今考えてること」を言葉にするだけでも、相手は判断しやすくなります。 - Q2:AIに詳しくないですが、うまく伝えられますか?
A:むしろ経験がある人ほど、背景情報の宝庫です。伝え方さえ整えれば、AIはその知見を活かせます。 - Q3:そんなに詳しく書いたら、長くなりすぎませんか?
A:要点を5W1Hで整理すれば、むしろ短く伝えられます。 - Q4:相談と報告って、何が違うんですか?
A:相談は「一緒に考えてほしい」、報告は「もう決まってることを伝える」──目的の違いです。 - Q5:ChatGPTに何て話しかけたらいいかわかりません…
A:「こういうことで困ってます。こう考えてます。アドバイスください」でOK。丁寧すぎるくらいがちょうどいいです。
9. 次のアクション|「伝わる質問」の最初の一歩を
セレンデックではAIウェブディレクター育成講座を開催しています。ご興味ある方は是非ご参加ください。体験会、説明会も実施しています。
この逆質問フォーマットを、Custom GPTに組み込み、強制的に“考えさせる”設計も可能です。「慣れていない人でも漏れなく伝えられる」AIとの協業の第一歩としておすすめです。興味のある方はぜひお問い合わせください。
- 🧠【法人向け】AI時代の“考える力”を育てる
『AI Webディレクター養成講座』- ChatGPTやGeminiなどを活用した、ゼロから始めるAI仕事術
- Webの基本技術、ヒアリング・構成・提案・ライティング・AI活用の“ディレクション5技能”を実務に落とし込む
- Web初心者・未経験者でも、「考える力」と「伝える力」を体系的に学べる講座です。0からAIwebディレクターとして活躍できるまでをサポートします
- 💡【実践支援】AI導入から内製化までを設計
『AI・DX戦略構築講座(法人研修プラン)』- 現場で「なぜ進まないのか」を構造的に分析
- 部署別ヒアリングから始める“内製化の第一歩”
- 最新AIツールの活用例と、現場に定着させる教育設計をワーク形式で支援




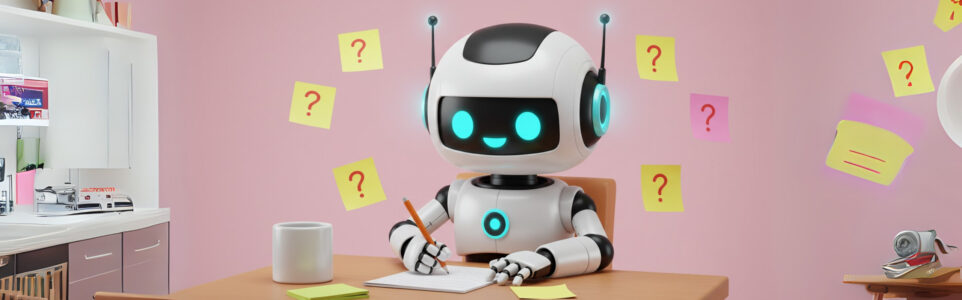




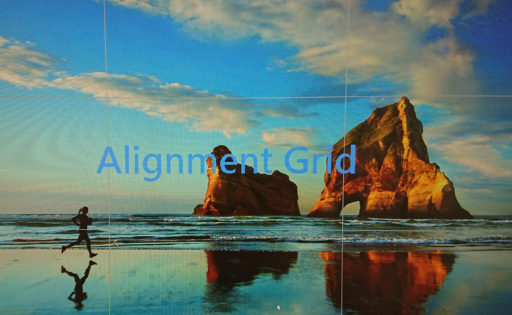






新しいサイトを考えてます。どうですか?