こんにちは。AI様に全面降伏して積極的に共存すると決めた、株式会社セレンデックの楠本です。
「AIで代替される仕事が増えてきた──」
そんな言葉が現実味を帯び始めたのは、僕自身がChatGPTを本格的に研究し始めた2023年のことでした。
正直に言えば、誰よりも早く飛び込んで、誰よりも早く衝撃を受けた自信があります。
たとえば、FigmaとChatGPTを連携してワイヤー構成を生成するプロセス──
これまで何時間もかけていた初期設計が、AIを通じて10分足らずで可視化されていく。
そのとき、僕の中にひとつの感情が湧きました。
もちろん、自分で試していた分、その精度や限界もわかっていたつもりでした。
でもそれ以上に、「AIが出してくる“それっぽい答え”が、人を納得させてしまう」ことに、ある種の焦燥を感じたのです。
でも、同時にこんな問いも浮かびました。
自分が“やらなくてよくなった仕事”があるなら、それは“やらなくてもよかった仕事”だったのでは?
そう思えた瞬間から、僕の中で“恐怖”は“実験欲”に変わっていきました。
この記事では、そんな「AIに自分の仕事を奪われるかもしれない」と本気で感じたディレクターとして、最初にやるべきこと、考えるべき視点を共有したいと思います。
──少しでも、あなた自身の“問い”のきっかけになれば嬉しいです。
「AIに仕事を奪われるかも」と感じたときに起きていること
「AIで作れるものが増えてきた」
「クライアントが自分でプロンプト書いてる」
「制作費が取れなくなってきた」
……Webディレクターの現場で、こんな声を聞くことが増えました。
特に中堅層ほど、「自分のポジションがどんどん狭くなるような感覚」を覚えているようです。僕もまさにそうでした。
でも、ここで一つだけ強く言いたいのは、
ということです。
ディレクションの中でも「段取り」や「伝言係」「資料づくり」などの定型業務は、確かにAIが得意です。
でもその一方で、AIが“絶対に触れられない領域”もあります。
それは、「問いを立てる力」と「人の温度がにじむ判断」です。
つまり、僕たちがやるべきは──
なのかもしれません。
Webディレクターが「最初に」すべきことは何か?
正直、多くの人がこのように思い、焦るのかと思います。
「AIリテラシー」とか「プロンプト エンジニアリング」とか、
勉強すべきことが多すぎて、何から手を付けたらいいかわからない──。
でも大丈夫です。実際、私が最初にやってよかったのは、
これは見た目よりずっとパワフルな作業です。
「やってる風だけど、実は付加価値が薄い業務」って、案外たくさんあったりします。
- クライアントからのヒアリング → AIでは代替不可(感情・文脈)
- 要件定義書の作成 → AIで下書きOK(確認・調整は人)
- タスク管理 → AI+Notionで半自動化可能
- 進行中の意思決定 → 人の判断が必要
- 企画立案 → AIと“共創”する形が最適
──全部を奪われるわけじゃない。
むしろ、“うまく委ねる”ことで、自分が本来やりたかった「クリエイティブな部分」に集中できるようになるんです。
Webディレクターの仕事はAIに代替される、そう感じている方も多いかもしれません。しかし、全てがAIに置き換わるわけではなく、一部の定型業務はAIによって効率化されつつあるのが現状です。これは悲観すべきことではなく、むしろ好機と捉えるべきです。AIが不得意とする「文脈理解」「感情配慮」「現場判断」といった人間ならではの領域に集中することで、Webディレクターとしての価値をさらに高めることができます。AIは私たちから仕事を奪う存在ではなく、私たちの能力を拡張し、新しい可能性を切り開いてくれるパートナーなのです。
「AIと共創できる人」になるための第一歩
“共創”というと大げさですが、要は「AIを使う前提で、自分の価値を再定義する」こと。
その第一歩は、自分がやっている仕事に「問いを立てる力」を持つことでした。
- このタスクは、なんのためにある?
- この判断は、誰がするべき?
- これって、言い換えればどんな意味?
──こういった“問い直し”を続けると、AIの得意不得意が見えてくるんです。
逆に言えば、
言葉を選ばずに言えば、
「“指示待ちディレクター”の時代は、静かに終焉を迎えつつある」のかもしれません。
でも、それは悲観ではなく“進化の入り口”です。
AIは単なるツールではなく、私たちの仕事のあり方そのものを変えようとしています。この変化に対応するためには、AIの技術を学ぶことも大切ですが、それ以上に「なぜこの仕事をするのか」「このタスクの本当の目的は何か」といった本質的な問いを立てる力が求められます。AIは与えられた作業を効率的にこなしますが、問いを立てることはできません。だからこそ、問いを立てる力こそが、これからの時代に人間が持つべき最も重要なスキルと言えるでしょう。この力を身につけることで、私たちはAIを使いこなす側、つまり「共創」する側へとシフトできるのです。
変化を乗り越えた先にあるもの──不安から“問い”への転換
不安はなくなりません。むしろ、新しいAIのリリースニュースを見るたびに、「また何か変わるのか…」と身構えてしまう自分がいます(笑)
でも、今は少しだけ、構え方が変わってきました。
それは、
というスタンスを、自分なりに確立しつつあるからです。
実際に社内で試してみると、AIツールにも“向き不向き”があります。
- ChatGPT:構成案や原稿の草案には便利。でも情報の裏取りは人力が必要。
- Notion AI:日報や議事録の下書きが爆速に。でも感情ニュアンスはやや弱い。
- Midjourney:ビジュアル案出しには強いが、細かい意図伝達には工夫が必要。
こうした特性を知るほどに、「AIと“どう付き合うか”を設計できる人が、次の現場を作っていくんだな」という実感が強くなっていきました。
そして、そこには“問い”が必要なんです。
自分の中に「問い」があるかぎり、価値は奪われない
僕が今, 確信しているのは、
ということです。
問いとは、「なぜそれをやるのか」「何のためにやるのか」を掘り下げる力。
この問いが深い人は、AIが何を出してきても「使う側」に回れます。
逆に、問いのないままAIに丸投げすると、
それこそ“奪われる側”に陥ってしまう。
──だからこそ、
というのが、僕の今の答えです。
まとめ:まずは“問い直す”ことから始めよう
AIに仕事を奪われるかもしれない──。その不安は、ごく自然なものです。
でも、そこに留まり続ける必要はありません。
まずやるべきは、
- 自分の業務を“問い直す”こと
- AIとの“線引き”を可視化すること
- そして「共創」という選択肢に、一歩踏み出すこと
です。
完璧じゃなくていい。試行錯誤しながらでいい。
でも、「問いを持ち直すこと」さえ忘れなければ、
人は必ず“使う側”に立ち戻れます。
──一緒に、その一歩を踏み出しませんか?
この気づきが、どなたかの役に立てば嬉しいです。
セレンデックではAIウェブディレクター育成講座を開催しています。ご興味ある方は是非ご参加ください。体験会、説明会も実施しています。
- 個人向け:AI時代の“考える力”を育てる
『AI Webディレクター養成講座』- ChatGPTやGeminiなどを活用した、ゼロから始めるAI仕事術
- Webの基本技術、ヒアリング・構成・提案・ライティング・AI活用の“ディレクション5技能”を実務に落とし込む
- Web初心者・未経験者でも、「考える力」と「伝える力」を体系的に学べる講座です。0からAIwebディレクターとして活躍できるまでをサポートします
- 法人向け:AI導入から内製化までを設計
『AI・DX戦略構築講座(法人研修プラン)』- 現場で「なぜ進まないのか」を構造的に分析
- 部署別ヒアリングから始める“内製化の第一歩”
- 最新AIツールの活用例と、現場に定着させる教育設計をワーク形式で支援
よくある質問(FAQ)
- Q1. Webディレクターの仕事はAIに代替されるのでしょうか?
A. 一部の定型業務は代替されつつありますが、「文脈理解」「感情配慮」「現場判断」などの領域はAIには難しいため、共存の可能性が高いです。 - Q2. AIを学ぶ時間がありません。何から始めたらいいですか?
A. まずは「自分の業務の棚卸し」から。次に、ChatGPTやNotion AIなど、触ってみて“感覚を掴む”ことがおすすめです。 - Q3. AIが怖くて、なんとなく距離を取ってしまいます…
A. それも自然な反応です。「正しく恐れ、正しく使う」を意識することで、不安は“判断軸”に変わります。 - Q4. 若手とのスキルギャップが怖いです…
A. 若手は吸収力がありますが、「判断・文脈・感情」の部分で経験値が生きます。焦らず、自分の強みを見直すことが大事です。 - Q5. セレンデックの支援内容を知りたいです
A. 「AIディレクター講座」や無料の業務内製化支援などを行っています。LINE登録いただければ、個別相談も可能です。
──あとは、とにかくやってみるだけです!まずは行動してみましょう。とりあえずでも始めると見えてきます。










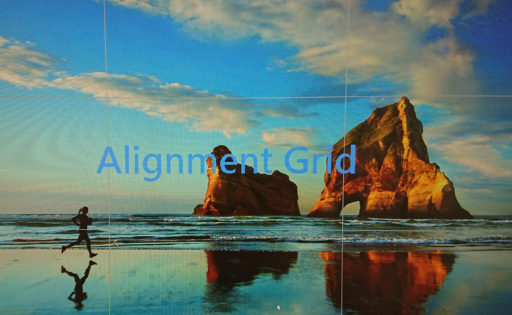





……え、これ、俺の仕事、もうAIでできるやん