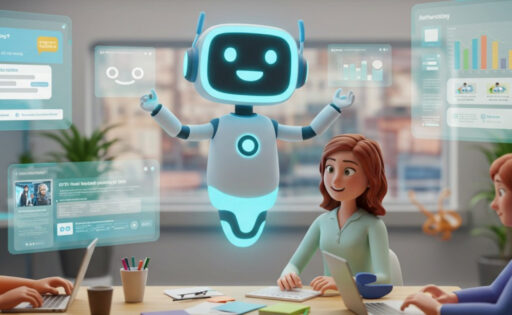解説YouTube動画はこちら 【AIで劇的に成果を上げる秘訣は“業務の工程把握と設計力”】
AI導入は“選び方”で9割決まる──現場で“使える”AIツール・ベンダー選定の5原則【2025年最新】
こんにちは。「AIでこんなことが出来るんだすごーい!」 ではなく、AIは現場で使えてなんぼやで、株式会社セレンデック代表の楠本です。
「AIってすごい(らしい、詳細はようわからんけど・・)。で、うちの現場でどう使えばいいの?」──こんな声、聞いたことありませんか?
技術としてのAIは確かに進化しています。でも、それが“現場に根づいて価値を生むかどうか”は、まったく別の話です。
私自身、Web制作やマーケティングの現場に長く関わってきて、「すごい技術」を「実際に使えるもの」にする難しさを痛感してきました。
今回は、AIツール・ベンダー選定で失敗しないために押さえるべき“5つの原則”を、現場視点×一次情報ベースでお伝えします。
1. AI導入前に“業務目標”と“成果数値”を明確化する【業務フロー再設計】
「AIを使いたい」──それ自体は素晴らしい第一歩です。
でも本当に必要なのは、「何をどう変えたいのか?」を明確にすることです。
たとえば:
- 月40時間の事務作業を削減したい(=年間480時間の人件費圧縮)
- 提案書の作成時間を30分→5分に短縮したい(=1人当たり月10時間の余力創出)
- 顧客対応の品質を一定以上に保ちたい(=対応時間と満足度のバランス最適化)
こうした“数値で測れる業務改善ゴール”があると、選ぶツールも、依頼するパートナーも、ぶれません。
レシピがないのに調味料を探す──それがAI導入の失敗あるあるです。2. 「紹介できる人」ではなく「業務に組み込んだ人」を選べ【AIコンサル選定基準】
「このツール、こんなことができます!」と機能紹介だけする人や会社──最近、本当に多いです。
でも、それだけでは現場には落ちません。私が言いたいのは、「ツールを紹介する人」ではなく、「実際に導入し、組織に根づかせたことがある人」と組むべきだということです。
なぜか?
AIツールは導入するだけなら簡単です。でも、そこから業務再設計に落とし込み、社内で定着させ、使い続けられる構造をつくることが最も難しい。
私自身、ツール導入後に“現場が使わない”という事態を何度も経験してきました。
- 評価制度とズレて「AIを使うだけ損」になっていた
- 担当者の理解が浅く「結局、従来の方法で戻っていた」
つまり、ツール知識より「業務・人・文化」にまで踏み込める実践者であるかが重要なんです。
3. 「使わせる仕組み」がなければAIは現場で死ぬ【社内展開と評価制度】
AI導入が形骸化する理由の多くは、「使わなくても困らない」状態が続いてしまうことにあります。
便利なツールを入れても、
- 評価に繋がらない
- 誰も使っていない
- 使い方を教える人がいない
──このような環境では、AIは“飾り”で終わってしまいます。
そこで必要なのが、人が使いたくなる仕組みです。例:
- 「AI活用で業務時間が短縮されたら、評価加点する」
- 「毎週、活用事例をチームで共有する会を設ける」
- 「AIを使った工夫を“見える化”して表彰する」
セレンデックでも、実際にPlaud(議事録AI)を導入したチームにインセンティブを設け、活用率がわずか3週間で87%に到達したという事例があります。
4. AIツールは“多機能オールインワン”より“連携と分担”で選ぶ【ツール選定・組み合わせ例】
AIツールの世界には、“一つで何でもできるツール”という幻想がつきまといます。
でも現実は、目的ごとに分担・連携して使う方が圧倒的に成果が出るというのが、私の実感です。
実際にセレンデックでは:
- Plaud(音声→要約)→ChatGPTで骨子・構成を作成→Gammaでプレゼン資料化
──というフローで、1案件あたりのドキュメント作成時間を約60%削減しました。
主なツールの組み合わせ例(2025年最新)
| 用途 | ツール |
|---|---|
| リサーチ・検索 | Perplexity、Komo.ai |
| 骨子・文章作成 | ChatGPT、Claude |
| 音声→文字起こし・要約 | Plaud、Notta |
| 資料・提案書 | Gamma、Tome |
| 動画作成 | Heygen、Synthesia |
| デザイン・SNS画像 | Canva、ジェーンズパーク |
──このように、“適材適所”でツールを使い分ける設計こそが、実務で成果を出す鍵なんです。
5. “それ、本当に必要?”──ツールの中身と構造を見抜く眼を持つ【選定リテラシー強化】
最近、見た目が洗練されたAIツールが増えています。
UIが美しく、説明も賢そう──でも中身を見てみると…- 実は、ChatGPTに同じことを聞けばほぼ同じ答えが返ってくる
そんなケース、非常に多いです。
これは技術的には「APIラッパー型」と呼ばれる仕組みで、既存のAIエンジン(例:ChatGPT)に質問を送って、その答えを整形して返すだけの仕組みです。もちろん、それが悪いわけではありません。
ただ、それを「すごそう!」という見た目や謳い文句だけで導入してしまうと、コストだけが増えて実務には活かされない。
大事なのは、「これは何をしているツールなのか?」を構造的に理解することです。
✅ 選定のためのチェックポイント:
- 自社の業務フローに合っているか?
- それを自分でやれば実現できないか?
- 継続コストと効果のバランスは合っているか?
たとえばセレンデックでは、ChatGPTのプロンプト設計を社内で内製することで、月額約5万円かかっていたツール類の代替を月1,000円未満で再構成した事例もあります。
【まとめ】“使えるAIツール”ではなく、“使える状況と仕組み”を設計する
AI導入の本質は「すごいツールを選ぶこと」ではありません。
それを、現場で定着させて使い続けられる“構造”をつくること。
そのためには、以下の視点が欠かせません:
- 目的と成果を“数値”で明文化(KPI設定)
- 経験者と組み、業務レベルで再設計(ベンダー選定眼)
- 「使いたくなる構造」をつくる(評価・共有・可視化)
- 複数ツールを連携して活かす(組み合わせ設計)
- ツールの中身・コスト・構造を見抜く(リテラシー)
セレンデックでは、こうした現場に根づくAI活用支援を、机上の理論ではなく“やってみてわかったこと”として支援しています。
まずは、「うちの業務、どこからAIにできる?」という問いから。
また、社内のAI活用リテラシーをどう高めていくかについては、別記事「社内AIリテラシーを高める方法」に詳しくまとめていますので、あわせてご覧ください。
一緒に、“現場で使える仕組み”から整えていきましょう。一緒にAI使って盤がっていきましょう!!
- 個人向け:AI時代の“考える力”を育てる
『AI Webディレクター養成講座』
- ChatGPTやGeminiなどを活用した、ゼロから始めるAI仕事術
- Webの基本技術、ヒアリング・構成・提案・ライティング・AI活用の“ディレクション5技能”を実務に落とし込む
- Web初心者・未経験者でも、「考える力」と「伝える力」を体系的に学べる講座です。0からAIwebディレクターとして活躍できるまでをサポートします
- 法人向け:AI導入から内製化までを設計
『AI・DX戦略構築講座(法人研修プラン)』
- 現場で「なぜ進まないのか」を構造的に分析
- 部署別ヒアリングから始める“内製化の第一歩”
- 最新AIツールの活用例と、現場に定着させる教育設計をワーク形式で支援
※関連記事: