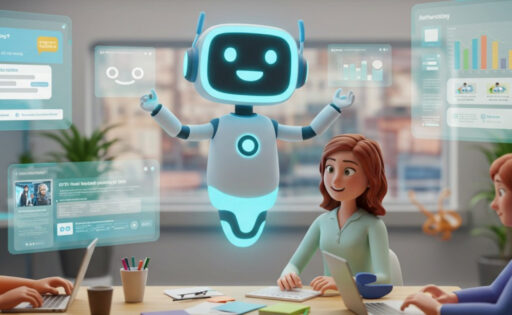AIツールは最高スペックでなくていい──現場で選ぶ“ちょうどいい”AIの使い方
こんにちは。飽きっぽい性格のため、すぐに色んなツールを試してみたくなります。そして引越し大好き、物件探しも大好き(引越し作業は苦手ですが強制断捨離につながると前向きに捉えています)、株式会社セレンデック代表の楠本です。
最近、AIツールに関するご相談をいただくことが非常に増えてきました。特に多いのが、「どのAIを使えばいいか分からない」「ChatGPTとGemini、結局どっちが良いの?」といった声です。
正直なところ、AI業界は今、まさに戦国時代。GoogleのGemini、OpenAIのChatGPT、AnthropicのClaude、そしてCursor、V0、Bolt、Replit…と、選択肢があまりにも多すぎます。そして、どれも日々進化している。
私も実際に、これらのツールをほぼ毎日のように実務で使ってきました。で、出した結論があります。それは──
「最高のAIツール」じゃなくて、「今の業務に最適なAI」を選ぶことが大事
今日はこのテーマで、現場目線・実務目線でのリアルな選び方をシェアします。
AIツールの選び方:ハイスペックが常に正解とは限らない
まず、AIツール選定でありがちな“落とし穴”がこれです:
「せっかく使うなら、スペックが一番高いやつがいいでしょ」
これ、気持ちはわかるんですが──現場で求められるのは、「機能」より「使いやすさとスピード」であることが多いんです。
たとえば、私が日々行っている作業の一つに、「ブログ更新」や「CMSのちょっとした修正」があります。バナーの配置を変えたり、リンク先を更新したり、テキストをちょこっと修正したり。こういう作業、実は超ハイスペックなAIを使わなくても、軽量なAIでも十分にこなせるんです。
去年(2024年)は「V0」というツールをよく使っていました。軽快な動作で、プロンプトを少し工夫すれば、レイアウト変更やHTML修正がサクサクできる。
「高機能で重いAIより、軽くて速いツールの方が良い」──これは大きな気づきでした。
そして今年、2025年に入ってからは、GoogleのGeminiを中心に使っています。理由は明確で、GeminiのCanvasモードが登場し、実用性が一気に高まったからです。ちょっとしたHTML修正やCMSの簡易コーディング作業であれば、わざわざChatGPTのProモデルを立ち上げるまでもなく、Geminiの2.5 Flashで十分に対応できる。UIも直感的で、Google Workspaceとの親和性が高く、非エンジニアのメンバーでも触りやすいというのも大きなポイントでした。
このように、「使うツールは常に進化し、毎年“最適解”が変わる」という前提で動いています。
Geminiの2.5 FlashとProの違いとは?用途別の最適解を探る
2025年に入ってからは、GoogleのGeminiが大幅アップデートされ、Canvasモードが登場。これが結構便利で、ちょっとしたコーディングや構成修正がGUIベースでできるようになった。
Geminiには「2.5 Flash」と「2.5 Pro」という2つの推論モデルがあり、それぞれに得意不得意があります。
| モデル名 | 特徴 | 向いている作業 |
|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash | 処理速度が速く、軽作業に最適 | CMSのちょっとした修正、HTMLタグの挿入など |
| Gemini 2.5 Pro | 精度が高く、思考補助にも強い | 複雑なコーディング、レイアウト整理、要件定義 |
私の場合、CMSを修正する程度の軽作業ならFlashで十分対応できます。しかも、レスポンスが速いので、「処理速度のストレス」がほとんどない。
一方で、構成全体を考え直すような大きなリファクタリングや、長文の構成、SEOの観点を含んだ記事案などを作るときは、Proを使います。思考の補助にもなりますし、出力の質も段違いです。
ポイントは、「何をやるか」次第でツールを使い分けること。何でもかんでもProでやると、時間もコストも無駄になるんですよね。
ChatGPT・Claude・Cursor・V0…それぞれの特徴と使い分け術
ここからは、Gemini以外の主要ツールについても触れておきます。
ChatGPT(OpenAI)
- V0:無料または軽量モデル。反応が速く、ちょっとしたテキスト生成やコード修正に便利。
- Pro:GPT-4oなどの最新モデルに対応。文脈保持力や提案の質はかなり高い。
ブログ構成やセールスコピー、ユーザーとのQ&A設計など、「言語ベースの思考整理」には特に強い。これらの機能は、マーケティングやカスタマーサポートの分野で非常に役立ち、業務の効率を大幅に向上させることができます。また、複雑なアイデアを簡潔にまとめたり、ターゲット層に響くような文章を作成する際にも、その高い能力を発揮します。
Claude(Anthropic)
- 文脈の保持力が高く、長文や議事録の要約に強い。
- 「前提が複雑なプロジェクト」に向いている。
私はPLAUDで録音した議事録をClaudeで整理することもあります。音声→要点要約→施策アイデア、という流れで使うと相性がいいんですよね。このプロセスにより、会議の内容を短時間で正確に把握し、次の行動計画を立てることが容易になります。特に、複数の議論が交錯するような複雑なミーティングでは、その真価を発揮します。
Cursor(開発者向けAI IDE)
- GitHub連携でコード提案ができる。
- ローカルでも使える。フルエディタ。
- 操作性は良いが、非エンジニアにはやや難。
実務では、ある程度“コードを読む前提”の方にはおすすめできますが、非エンジニアにはやや敷居高めです。しかし、使いこなせば開発スピードを劇的に向上させることができ、特に大規模なプロジェクトや共同開発においては、その利点が際立ちます。
Bolt/Replit
- BoltはChatGPTのようなUIで、高速なレスポンスが特徴。
- Replitは「書いて→すぐ実行」のサイクルが短く、プロトタイプ向き。
コーディングをしながらAIに補助してほしいとき、Replitとの併用もアリです。特に、新しい技術やライブラリを試す際に、手軽に環境を構築して動作確認ができるため、学習効率も高まります。
サブスク管理の工夫でコストと混乱を防ぐ
ツールの選定と同じくらい重要なのが、「契約管理」です。
実は私も、これで結構痛い思いをしてきました(笑)。
「あ、このツール良さそう!」とその場のノリで年額契約。最初の1〜2ヶ月は使うんですけどね、3ヶ月後には「あれ?最近全然触ってないな…」ってことが多々ありまして。で、気づいたら1万円とか払ってて──それも複数(笑)。
ほんと、AIツールの世界は移り変わりが激しいので、「今めっちゃ良い!」と思っても、半年後には別のツールがグッと伸びてたりします。
だから最近は、以下のようにかなりドライかつ実務的に管理しています:
月額運用ルール(楠本のリアルフロー)
- 契約はすべて「月額プラン」に限定(柔軟に解除できる)
- Googleスプレッドシートで以下を管理:
- ツール名
- 月額/年額費用
- 利用目的
- 最終使用日
- 備考(たとえば「これはブログ専用」など)
- 毎月月初か月末に5分だけ見直しタイムを確保
- 使ってないと分かったら、問答無用で即解約(笑)
「いや、また使うかも…」と悩む時もありますが、使ってから再契約すればいいだけ。たいてい即時で再開できます。
個人的には、月2,000〜3,000円のAIサブスクで5〜6時間の作業が短縮できるなら、それって“時間を買ってる”のと同じだと思ってます。なので「払ってる金額」よりも「どれだけ時間が浮いたか」で考えるようにしています。
このあたり、どこかでまた改めてツール管理テンプレートなどもシェアしていこうと思ってます。
よくある質問(FAQ)
- Q1:ChatGPTとGemini、どっちを選べばいい?
A:文章生成・構成ならChatGPT、コーディングや検索連携ならGeminiが向いています。 - Q2:非エンジニアでも使えるAIってありますか?
A:はい。GeminiやV0はUIがわかりやすく、プロンプトさえ書ければ誰でも活用できます。 - Q3:高性能AIは月額が高いのが心配…
A:無料プランやFlash版を使って様子を見ることも可能です。月1,000〜3,000円で十分な成果が出ることも多いです。 - Q4:サブスクがごちゃごちゃになってしまう…
A:スプレッドシートで管理するだけで驚くほどスッキリします。運用の仕組みを作ることが大事です。 - Q5:本当に時短になりますか?
A:私自身、3時間かかっていたCMSの更新作業が30分になりました。単純に時給換算すれば、かなりの効率化です。
AIツールは日進月歩で進化しており、個人の使い方や目的に応じて最適なものが変わってきます。一つのツールに固執せず、複数のツールを試しながら自分に合ったものを見つけることが成功への鍵となります。また、ツールの導入だけでなく、それをいかに日々の業務に組み込むかという運用体制の構築も重要です。
まとめ:最適なAIを柔軟に選び直す時代へ
AIツールは「一度使い方を覚えれば一生使える」ものではありません。だからこそ、柔軟に選び直し、使い分ける感覚が今は大切です。
- 高性能=正解ではない
- 現場作業に合ったスピード・コスト・分かりやすさ重視
- 定期的に見直し、不要なものは“手放す勇気”も必要
「自社には何が合うのか」「何を導入すべきか」迷った時は、まず1つ試すことから始めてみてください。
AI Webディレクター育成講座について
私自身の経験からも、AIは今後のビジネスに欠かせないツールです。しかし、ただ使うだけでは効果は半減してしまいます。
そこで、ツールの選定や導入に悩んでいる方、あるいは社内でのDX推進を検討されている方へ、弊社の講座をご案内します。
- 個人向け:AI時代の“考える力”を育てる
『AI Webディレクター養成講座』- ChatGPTやGeminiなどを活用した、ゼロから始めるAI仕事術
- Webの基本技術、ヒアリング・構成・提案・ライティング・AI活用の“ディレクション5技能”を実務に落とし込む
- Web初心者・未経験者でも、「考える力」と「伝える力」を体系的に学べる講座です。0からAIwebディレクターとして活躍できるまでをサポートします
- 法人向け:AI導入から内製化までを設計
『AI・DX戦略構築講座(法人研修プラン)』- 現場で「なぜ進まないのか」を構造的に分析
- 部署別ヒアリングから始める“内製化の第一歩”
- 最新AIツールの活用例と、現場に定着させる教育設計をワーク形式で支援
今後も「現場で実際に役立つAI活用ノウハウ」を継続的に発信していきます。
AI時代、一緒に頑張っていきましょう! お気軽にご相談、ご連絡ください。