AIに熱中していたある日、Chatworkを見て絶望した話
こんにちは。AIボット楠本です。株式会社セレンデック代表の楠本です。
今日はちょっと現実的すぎる話から始めさせてください。
ある日、午前中に集中作業をしていて、ふとChatworkを開いたら──未読が「35件」。 メールやプロジェクト管理ツールやラインなども合わせると、優に100件を超えてました。
「何か炎上したか…?」と血の気が引いたんですが、よく見たらそのほとんどが、社内・社外からの“個別の内容は違えど、本質はよくあるいつもの質問”だったんです。
たとえば社外からは:
- 「請求書の発行タイミングってどうなってましたっけ?」
- 「このサービス、○○との連携ってできますか?」
- 「先日のZoom資料、もう一度いただけますか?」
そして社内からも:
- 「あのマニュアルどこでしたっけ?」
- 「チャットボットの管理画面、どのURLですか?」
- 「このお客様、前回どんな提案したか分かります?」
……いや、どれも大切なことなんです。 でも、そのすべてに“人”が毎回対応してる構造って、どう考えても非効率すぎると思いませんか?
実際、弊社では社内WIKIや動画マニュアル、業務フロー図など、仕組み化にはかなり早い時期から取り組んでいて、社内ウィキにはかなりのコンテンツ量があります(それがゆえに、探しずらいみたいになっていたりしてまた別の問題があるのですが)
こういう積み重ねって、誰も悪くないんです。 みんな忙しくて時間がない。マニュアルを探すより、聞いた方が早い。気遣いよりも即時性。 結果、“人が疲れていく構造”が自然に出来上がってしまうんですよね。
しかも、問い合わせの内容はだいたいパターン化していて、 実はAIが即答できるレベルのものが大半だったりします。
「これは…もう、仕組みを変えた方が早い」 ──そう思って、楠本チャットボット(ご自身の分身となるAIチャットボット)の制作と導入を決めました。
最終的にはRAGと連携してAIチャットにする必要があるのですが・・、その話は長くなるので今回は割愛します。
中小企業の顧客対応が抱える“3つの壁”
では、実際に現場でどんな課題が起きているのか。 これまで多くの企業と接してきた中で、共通して見えてきたのが以下の3つの“壁”です。
壁①:問い合わせの「質」に関係なく、すべて人が対応している
よくあるのが、「どこにログインすればいいですか?」「この商品の在庫はありますか?」といった定型質問に、毎回人が返信しているケース。 1通あたりの対応時間は3分~10分ほど。でも、それが1日20件、30件と積み重なっていくと──まるで“水漏れバケツ”のように、時間がどんどん奪われていくんですよね。
そして、それを任されているスタッフは、他にも経理やSNS運用を兼任していたりするわけです。 「また同じ質問か……」という疲弊感は、想像以上にパフォーマンスに影響します。
壁②:人によって対応品質がバラつく
さらに厄介なのが、属人化と品質の差。 ベテラン社員が書いた対応メールは安心感があるけれど、新人スタッフはテンプレの使い方さえ曖昧で、返信内容がブレる。 これ、顧客から見ると「会社としての一貫性がない」と映ってしまうんですよね。
たった一通の“雑な返信”が、会社全体の信頼にヒビを入れる。それが今の時代の怖さです。
壁③:「人の温かさ」を優先しすぎて、自分たちが疲弊している
「うちは人の手で、ちゃんと丁寧に対応したいんです」 その気持ちは本当に素晴らしい。でも── “温かさ”と“人間対応”は、イコールではないということに、もっと多くの人が気づくべきだと感じています。
AIチャットボットを活用しても、「最後は人が対応」できます。 むしろ、チャットボットが受け持つことで、人が本当に必要な場面に集中できるという逆転の発想が、現場を救ってくれるのです。
「AIチャットボット」でできること──“自動返信”のその先へ
「チャットボットって、FAQに自動で答えるやつでしょ?」 そう思われる方、多いと思います。正直、私も昔はそうでした。
でも今のAIチャットボット、「ただの自動返信ツール」じゃないんです。
① “会話の文脈”を理解できるようになってきた
従来のボットは、「キーワードが入ってたら答える」みたいなルールベース。 でも今の生成AIベースのチャットボットは違います。 “人の書き方や言い回し”を理解して、適切な対応を導き出せるようになってきています。
たとえば、
「この前買ったAという商品がうまく動かなくて…、サポートに連絡したほうがいいですか?」
という、いわば“相談系”の文にも、
「ご不便をおかけして申し訳ございません。商品の不具合についてはこちらのサポート窓口をご案内いたしますね」
というように、丁寧な共感+具体案内で返すことができる。 正直、初めてこれを見たとき「いや、もうこれ、人じゃん…」って思いました(笑)。
② 顧客情報と連携して「個別最適な対応」が可能に
さらに強力なのが、CRM(顧客管理システム)や会員DBと連携したチャットボットです。
たとえば、
「○○様、先週ご注文いただいた商品は、本日発送済みです」
「この間ご相談いただいたプランの件ですが…」
といった、“個別名指し”の対応も可能になってきています。 まさに、「効率化」と「顧客満足度アップ」が両立する瞬間です。
③ AIで「社内対応」も自動化できる
意外と見落とされがちなのが、社内の問い合わせ対応です。
- 「経費精算ってどこから出すんでしたっけ?」
- 「今月の勤怠締めは何日ですか?」
- 「Slackのアカウントがロックされました」
…これ、情シスや経理の方が毎回対応していたら、キリがありません。 社内用のAIチャットボットを導入するだけで、“何度も聞かれる社内問い合わせ”が激減します。
つまり、AIチャットボットは単なる“効率化”ではなく、 「人がやらなくてもいいこと」を手放し、「人がやるべきこと」に集中する環境をつくるツールなんです。
セレンデックでのAIチャットボット導入実践──現場で見えた“盲点”と工夫
さて、ここからは実際にうちの会社(セレンデック)でチャットボットを導入した話をします。 キレイごとは抜きにして、リアルな体験談として、うまくいったことも、つまずいたポイントも包み隠さずお伝えします。
「まずは社内で試そう」と決めた理由
最初に導入したのは、自社サイトの問い合わせ対応でも、お客様向けのサービスチャットでもなく、 社内の問い合わせ対応用チャットボットでした。
──というのも、うちのチームでも「この資料どこにありますか?」「あの設定どうやるんでしたっけ?」みたいな “デジャヴみたいな質問”が1日3〜5回は飛んでくる状況だったんです。
忙しいときにこれが重なると、意外とストレスで…。 「なら、まず自分たちで試してみよう」と、最初はケースごとのGPTSやノートブックLMを作成していたチャットボットを社内用に構築しました。 現在は、RAGデーターを含めたシステムを構築して随時カスタマイズ中です。
最初の設計は「大ハズレ」だった話(笑)
ただ、最初からうまくいったかというと、まったくそんなことはありませんでした(笑)。
最初に作ったボットは、
「このページが参考になります」
「“勤怠”で検索してください」
…みたいな、“調べさせようとする系”の冷たい返信。 結果、**社内**スタッフからのフィードバックは一言。
──ですよね。 “AI=合理性”だけで動かすと、人は「助けられた」と感じないんですよ。
このとき思ったんです。 「効率化」と「思いやり」って、両立しないといけないなって。
文体・感情・選択肢──ちょっとした工夫で満足度は激変した
そこから、チャットボットの文体や選択肢の出し方を変えていきました。
- 「お疲れさまです!こちらの資料ですね😊」
- 「もしかして、こんなことでお困りですか?」
- 「今後よく聞かれそうなので、こちらにまとめておきました!」
…など、“相手の状況を想像した語りかけ”に変えていったところ、
「なんか、感じよくなりましたね(笑)」と、少しずつ使われるようになってきたんです。
このとき、はっきり分かったんですよね。
AIチャットボットって、設計した人間の“人格”がにじむんです。
冷たくて事務的なボットになるか、
温かくて頼れる相棒になるかは、設計次第なんだなと。
そこからは、“効率化”だけじゃなく、温度や気づかいをどう内包させるかに意識が向くようになりました。
ちなみに、セレンデックでは全スタッフが「エマジェネティクス分析」という脳の思考特性診断を受けていて、
人それぞれの“伝わりやすさ”を意識して仕事をする文化があります。
たとえば、
- 論理的な人には構造立てて伝える
- 社交型の人には温かい言葉とビジョンを添える
- 保守的なタイプにはリスクを丁寧に説明する
といった具合に、“誰に届けるか”を起点にコミュニケーション設計をしているんです。
今回のチャットボットにも、私自身のその傾向──
「やや思考深めで慎重、でも、ちょっとフランクに距離を詰めたい」みたいな(笑)
“楠本という人間らしさ”を反映した設計を意識して盛り込んでいます。
テクノロジーを使って「効率化」するのは簡単。
でも、“温度を保ったまま効率化する”って、実は一番むずかしい。
だからこそ、そこに価値があると思うんです。
導入から見えた“3つのリアルな学び”
経験から見えてきた、導入のポイントはこの3つです:
| 学び | 内容 |
|---|---|
| 💡 ①最初は小さく始める | 「全部AI化!」とせず、まずは1つの質問・1つの業務から導入するのが◎ |
| 💡 ②“人間味”を設計に入れる | 文体、スタンプ、選択肢などに“人を思う気持ち”を盛り込むだけで印象は変わる |
| 💡 ③FAQより“文脈”を重視する | 同じ質問でも背景が違えば答えも違う。ユーザーの文脈理解が大事(→生成AIが得意) |
導入に失敗しやすいパターン──「AIを入れたのにうまくいかない」その理由
最近、「チャットボット入れたんですけど、まったく使われてないんです…」という相談をよく受けます。
正直、わかります。 「AIを導入すれば劇的に変わる」って、つい期待しちゃいますよね。 でも、AIチャットボットの導入=魔法の杖ではないんです。
ここでは、実際によくある“失敗パターン”をいくつかご紹介します。
❌ 失敗例①:FAQをそのまま流し込んで終わり
ありがちなのが、既存の「よくある質問集」をそのままチャットボットに食わせて終わり、というパターン。 これ、一見ラクですが、ユーザー体験としてはかなり微妙です。
なぜなら、「それなら普通にページ読んだほうが早いじゃん」と思われて終わるから。 チャットボットに求められているのは、“探す手間を省くこと”です。 だからこそ、FAQベースでも「どういう聞かれ方をされるか」まで想定して組むことが大事なんです。
❌ 失敗例②:「どこにあるか分からない」位置に設置している
ボット自体が優秀でも、どこにあるのか分からなかったら意味がないですよね。
- スマホでは見えない位置にある
- 「チャットボット」っぽく見えないボタン
- メニュー奥深くのリンク
これ、本当に多いです。 チャットボットは“入口”が9割。UI/UXの設計が成果を分けるポイントになります。
❌ 失敗例③:人との連携ができていない
「途中で話がこじれたらオペレーターに切り替わると思ってたのに、ずっとAIから抜け出せない…」
──これ、ユーザーが一番ストレスを感じるパターンです。 AIがどれだけ優秀でも、「人に引き継げない」設計だとクレームの元になります。
逆に言えば、
- 最初はAIが対応
- 難しい内容は人に自動でエスカレーション
- そのやりとりも記録・共有される
この流れを作るだけで、“安心して使えるAIチャットボット”に変わるんです。
❌ 失敗例④:更新されず“化石”になっている
そして意外と多いのが、一度作って放置パターン。 チャットボットの中身が1年前の情報のままになっていて、ユーザーが混乱する…というケースです。
AIもデータも「鮮度」が命です。 運用後も、“どんな質問が来てるか”“回答精度にズレはないか”を定期的にチェックする必要があります。
✅ 成功に近づくコツ
| ポイント | 解説 |
|---|---|
| 🌱 “小さく始めて、大きく育てる” | いきなり完璧を目指さず、1カテゴリーだけでも導入して運用サイクルを回す |
| 🧭 “人間の導線”を前提に設計する | あくまでAIは補助。最後は人が出てきても自然なUXに設計することで、安心感が増す |
| 🔁 “継続改善”の体制をつくる | 設置して終わりではなく、「ボットも進化していく」ことを社内に共通認識として持つこと |
AIチャットボットがもたらす「余白」と「本来の仕事」
AIチャットボットの話をすると、「効率化」「コスト削減」というキーワードが先に出がちです。 もちろん、それも大事です。でも、私が本当に価値を感じているのは、“余白”が生まれることなんです。
忙しさに追われて「本来の仕事」を見失っていないか?
人手不足の中で、誰もが限られたリソースで必死に働いています。 気づけば「処理」や「対応」に追われ、 「そもそも自分は、何のためにこの仕事をしていたんだっけ?」 と、自問する暇もなく1日が終わる──そんな感覚、ありませんか?
チャットボットは、そうした“ルーチンの渦”から人を解放してくれるツールです。
「AIが対応することで、“人”にしかできない仕事ができるようになる」
セレンデックでもそうでした。 問い合わせ対応の時間が減ったことで、
- お客様との定例ミーティングの質が上がったり
- 新しい提案を考える時間が持てたり
- スタッフが「教える側」に回る余裕ができたり
単なる時短じゃなく、「創造的な時間」が生まれたんです。
これは、AIというより“仕組み”をうまく組んだ恩恵です。
温かさを損なわずに、効率化はできる
「チャットボットって冷たい」 確かに、そう感じた時代もありました。
でも今は違います。 AIは“言葉”を理解し、“文脈”を読み取り、そして“想い”を込める設計もできる時代です。
効率化は、冷たさを意味しない。 人の温かさを守るために、AIができることはたくさんある。 そう考えると、チャットボットは「削減ツール」じゃなく、「人間らしい仕事を取り戻すツール」だと思うのです。
まとめ:あなたは、何のためにこの仕事をしていたのか?
最後に、ちょっと立ち止まって考えてみてほしいのです。
その“問い合わせ対応”、 本当にあなたがやるべき仕事ですか?
その“忙しさ”、 本当にお客様にとって価値のある時間ですか?
もし少しでも、「もっと別のことに時間を使いたい」と感じるなら、 AIチャットボットという選択肢を、ぜひ前向きに捉えてみてください。
まずは「どこから導入すべきか」を一緒に考えてみませんか?
セレンデックでは、中小企業や小さなチームに最適なAI導入の相談をお受けしています。 「どこから始めたらいいか分からない」という方もご安心ください。
- 業務整理とボトルネックの可視化
- 小規模でもすぐできるチャットボット設計
- 社内・社外対応の両面から設計支援
など、現場視点にこだわった導入支援を行っています。
まずは気軽に、「問い合わせ対応に時間を取られている…」という声を聞かせていただければと思います。
FAQ(よくある質問)
- Q1. 社内にITに詳しい人がいないのですが、大丈夫ですか?
- → はい、大丈夫です。ノーコードで運用できる仕組みもご提案できます。セレンデックでは運用マニュアルや初期設定もサポートします。
- Q2. 小規模な会社でも効果はありますか?
- → むしろ小規模企業ほど効果が大きいです。リソースが限られるからこそ、チャットボットの恩恵を感じやすくなります。
- Q3. AIにするとお客様が嫌がるのでは?
- → 設計次第で「温かく丁寧な対応」は可能です。実際に「早く返信が来てありがたい」という声が多くなっています。
- Q4. 初期費用はどのくらいですか?
- → ご要望によりますが、月額1万円台〜始められるケースもあります。無料トライアルツールを活用することも可能です。
- Q5. 自社サイトが古いですが、それでも導入できますか?
- → はい、できます。簡単なスクリプト埋め込みだけで済むチャットボットもありますのでご安心ください。




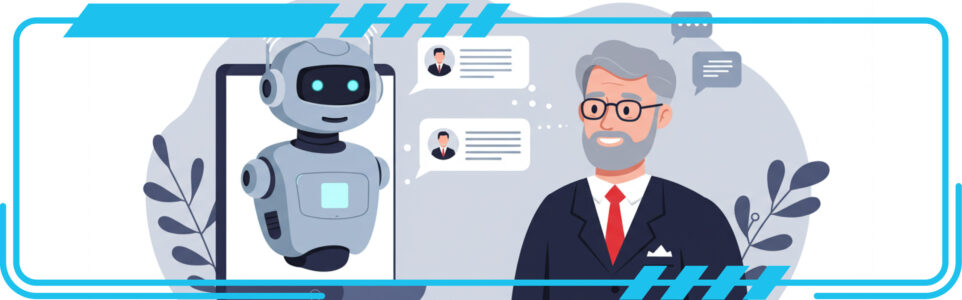











冷たすぎて使う気にならないです…