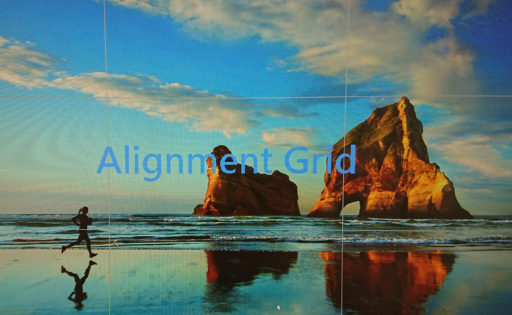解説YouTube動画はこちら 【AIの精度が悪くてイライラするあなたへ|ChatGPTが“サボる”理由と正しい対処法】
はじめに:AIが“サボり出す”あの瞬間、ありませんか?
正直に言うと──AIって、たまに「サボる」んですよね(笑)。
最初はめちゃくちゃ優秀だったのに、
こんにちは、株式会社セレンデックの楠本です。どんなときも、AIにも人間にも感情的にならずに常にジェントルマンでいられるよう努力しています。なかなかできないのですが・・
- 途中から返答が適当になったり、
- 質問しても「それはできません」と断られたり。
まるで人間みたいに、テンションが落ちてくる。
私も何度も経験しました。最初の頃は「今日は調子悪いのかな?」と思っていたんですが、
実はこれ、AIが怠けているわけじゃないんです。
AIの中で“情報が詰まっている”だけ。
チャットの履歴が増えすぎて、AIの「頭の中」がいっぱいになっている状態なんです。
──つまり、AIが“サボる”というより“疲れてる”んです。
なぜAIは途中で“適当”になるのか?
AIが突然、反応が悪くなったり、要約しかしなくなったりするのには理由があります。
代表的な原因は、この4つです。
| 原因 | 内容 | 対処法 |
|---|---|---|
| 🧠 文脈の肥大化 | 長時間やり取りを続けたことで、AIの記憶領域が膨張 | 一度リセットして引き継ぐ |
| 🔁 意図のズレ | 指示があいまいになり、AIが目的を見失う | 明確に目的を再提示する |
| ⚙️ 出力制限 | 文字数・UI(キャンバス等)の制約で途中カット | 分割出力の指示を出す |
| 💤 精度低下 | 内部負荷・セッション劣化 | 新しいAIに引き継ぐ |
要は、AIが「飽きた」んじゃなくて、構造的に疲弊しているだけ。
だから、感情的に「ちゃんとやってよ!」と叱るよりも、
“一度整理して引き継ぐ”方が確実に早いんです。
AIを切り替えるのは、気持ちの問題ではなく“整理と判断”の問題です。
AIがうまく動かなくなっても、つい「もう少し頑張れば直るかも」と思って続けてしまう。
でも、それは“気合が足りない”とか“諦めが早い”という話ではありません。
多くの人は“ここまでやったし”で続けてしまう。
でも本当は、“引き継ぐ”という発想がないだけなんですよね。
「ここまでやったし、もう少しだけ…」という惰性を合図に、一度整理して渡す。
それだけで、AIの精度もスピードも安定します。
MECEとは?──引き継ぎをうまくする“魔法の言葉”
AIに引き継ぎを頼むときに使えるキーワードがあります。
それが「MECE(ミーシー)」。
これは「Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive」の略で、
日本語では「重複なく、漏れなく」という意味です。
つまり、情報をきちんと整理してダブらないようにまとめる考え方。
AIに「これまでの内容をMECEで整理して」と伝えると、
AIは自動的に全体を漏れなくまとめてくれるんです。
この一言で、次のAIへの“引き継ぎ精度”が一気に変わります。
出力形式の選び方──人に渡す?AIに渡す?
AIに「整理して出して」と言うだけでは不十分です。
どんな形式で出すかを明確に伝えるのがコツです。
代表的なのはこの4種類:
| 形式 | 特徴 | 向いている用途 |
|---|---|---|
| JSON形式 | 構造化されたデータ。AIやシステムに渡すのに最適。 | AI同士の引き継ぎ・API連携 |
| YAML形式 | JSONより読みやすく、設定ファイルなどで使われる。 | AIと人間の中間用途 |
| CSV / TSV形式 | 表形式。Excelなどに読み込みやすい。 | データ収集・分析 |
| Markdown形式 | 見出しや箇条書きが読みやすい構造化テキスト。 | 人間への共有・確認 |
💡おすすめセット:
- AI用 → JSON形式
- 人間確認用 → Markdown形式
- 分析用 → CSV形式
この“二系統出力”が、AI運用を安定させるポイントです。
実際に使える「AI引き継ぎプロンプト」(コピペOK)
ここが実務の核心です。
AIがサボり出したら、この文章をそのままコピペしてください👇
🧩 AI引き継ぎテンプレート
これまでの内容を、MECE(重複なく・漏れなく)の原則に基づいて整理してください。
以下の2形式で出力をお願いします。
- JSON形式:構造化データとして、見出し・要点・結論・ToDoを含めること。
- Markdown形式:人間が読みやすい見出し構成で再整理すること。
出力が長い場合は、セクションごとに分割して「次へ」の合図で続けてください。
省略禁止・要約禁止。
これだけで、別のAIに切り替えても文脈がズレません。
“リセット”ではなく“引き継ぎ”に変わる瞬間です。
AIは「なんとなく続ける」より「整理して渡す」ほうがうまくいく
AIが詰まったら、リセットではなく“整えて渡す”。
それだけで流れが戻ります。
人間なら、「前に言ったアレの続きで…」で通じますが、
AIは空気を読みません(笑)。
だから、AI同士をつなぐときは、“なんとなく続ける”のではなく、
**「ここまで話した内容を整理して渡す」**だけで十分なんです。
これが、感情で続けるより、「整理してつなぐ」という考え方。
たったそれだけで、出力の安定性が劇的に変わります。
現場で気づいた「AIを叱るより、設計する」発想
私も最初のころは、「なんで最後まで出してくれないんだ!」と、ついAIにイライラしていました(笑)。
でもやってみて気づいたんです。
AIはサボっているんじゃない。
こちらの設計が曖昧なだけだったんです。
つまり、AIは“育てる”ものではなく、“設計する”もの。
どんなAIでも、構造を整えて渡せば、同じ精度で答えてくれる。
この気づきで、AI運用のストレスが一気に減りました。
実務で使えるポイントまとめ
- 💡 「判断」と「整理」で切り替える
- 🧩 MECE指定で抜け漏れ防止
- 🧱 JSON形式でAIに伝えやすく
- 📄 Markdown形式で人に見せやすく
- 🔁 分割出力+省略禁止で途中カットを防ぐ
これをテンプレート化しておくだけで、
「AIが途中で適当になる問題」はほぼ解決します。
よくある質問(FAQ)
- Q1. JSON形式って何?
A. JSON(JavaScript Object Notation)は、AIやシステムが理解しやすい「データの箱」です。文章を構造化して格納する形式で、情報が整理されたまま渡せます。 - Q2. Markdown形式でもOK?
A. OKです。人間に見やすい形で出せますが、AI処理には少し弱いです。「人間用+AI用」の2形式併用が最適です。 - Q3. 出力が途中で止まる原因は?
A. 文字数やキャンバス制限によるカットです。「分割して出して」と明示すれば止まりません。 - Q4. 引き継ぎはいつやる?
A. 「返答が短くなる」「要約ばかりになる」「拒否が増える」などの兆候が出たら即切り替えです。 - Q5. どのAIに引き継ぐべき?
A. ChatGPT、Claude、Geminiなど、使いやすいものを選んでOK。形式を統一しておけば、どのAIでも続けられます。 - Q6. MECEって難しくない?
A. 「ダブらず・漏らさずに整理してね」と伝えるだけで十分です。AIが自動的に整えます。 - Q7. どんな効果があるの?
A. 出力の安定・再現性の向上・ミス削減。AIの“気まぐれ”に振り回されなくなります。
まとめ:AIがサボったら、怒らず整える
AIが急にやる気をなくしたように見えたら、
それはAIの問題ではなく、“整理のタイミング”なんです。
だから、「叱る」でも「粘る」でもなく、
「整えて、渡す」だけ。
特別な決断はいりません。
必要なのは、“切り替えるという選択”と“整理の仕組み”だけです。
AIを“使う”ではなく、“設計する”。
この発想に切り替えた瞬間から、
あなたのAI運用は格段に楽になります。
「AIがサボったら、怒らず整える」
──この一言を頭に置いておくだけで、AIとの付き合い方が変わります。
次にAIが“適当”になったら、冷静にこう思いましょう。
「ああ、そろそろ引き継ぎの時間やね。」
【参考】セレンデックのAIディレクター育成支援
セレンデックでは、AI時代のビジネスに必要な「思考の整理と設計」スキルを習得する、
AIウェブディレクター育成講座を開催しています。ご興味ある方は是非ご参加ください。
体験会、説明会も実施しています。
- 個人向け:AI時代の“考える力”を育てる
『AI Webディレクター養成講座』- ChatGPTやGeminiなどを活用した、ゼロから始めるAI仕事術
- Webの基本技術、ヒアリング・構成・提案・ライティング・AI活用の“ディレクション5技能”を実務に落とし込む
- Web初心者・未経験者でも、「考える力」と「伝える力」を体系的に学べる講座です。0からAIwebディレクターとして活躍できるまでをサポートします
- 法人向け:AI導入から内製化までを設計
『AI・DX戦略構築講座(法人研修プラン)』- 現場で「なぜ進まないのか」を構造的に分析
- 部署別ヒアリングから始める“内製化の第一歩”
- 最新AIツールの活用例と、現場に定着させる教育設計をワーク形式で支援