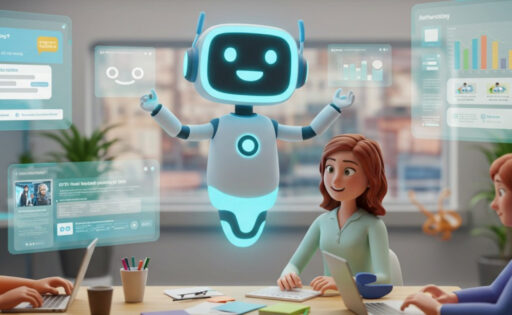こんにちは。「寝ているわけではありません、目を閉じて何も考えず、何にも反応しないで意識を飛ばして一時的に脳をリフレッシュうしているだけです」と仕事中には答えるようにしてます、株式会社セレンデック代表の楠本です。
本日はちょっと健康ネタ寄りのお話を。とはいえ、ビジネスにも直結する内容です。テーマは「集中力と酸素の関係」。
日常に潜む“なんかボーっとする”の正体
最近、仕事中に「なんか集中できないな」と感じることありませんか?
「寝不足かな?」「昼ごはん食べ過ぎた?」──もちろん、それも一因かもしれません。でも、私が日々体感しているもうひとつの要因があるんです。それが、“二酸化炭素(CO2)濃度”です。
ちょっとマニアックな話になりますが(笑)、私はオフィスに「CO2計測器(=二酸化炭素濃度測定器)」を常設しています。これ、地味に仕事効率に効いてくるんです。
なぜCO2が集中力を奪うのか?
科学的な研究でも、二酸化炭素濃度が集中力に影響を与えることが示唆されています。
Berkeley Labの研究では、1,000ppmで意思決定力が低下し、2,500ppmでは戦略的思考や主体性にも影響が出ることが確認されています。
出典: Berkeley Lab
ハーバード大学のCogFx研究では、CO₂濃度が500ppm上がるごとに反応速度や処理能力が2〜4%低下するという結果も報告されています。
出典: ハーバード大学 CogFx研究
University College London(UCL)も、CO₂濃度の上昇が記憶力や集中力の低下に関連する可能性を示唆しています。
CO2濃度の目安
- 400ppm前後:屋外レベル、理想的
- 600~800ppm:一般的な室内、問題なし
- 1000ppm超:眠気・集中力低下の可能性あり
- 1500ppm以上:換気推奨レベル
CO₂濃度が高まると、意思決定力、反応速度、処理能力、集中力、記憶力といった「脳のパフォーマンス」に明らかな低下が見られる──これは、ハーバード大学やバークレー国立研究所などの研究結果に基づくもので、ビジネスシーンにも直結する知見です。もちろん、体質や状況にもよりますが、「集中できないのは気のせい」ではなく、環境要因である可能性が高いという視点を持つことが重要です。
私の実験:CO2計測器を導入してみた
リモートワーク中心の私の執務環境では、基本的に一人なので600〜700ppmが平均値。
ところが、スタッフや来客があると一気に900ppm台へ。ミーティングが盛り上がってくると、すぐに1000ppm超えでアラートが「ピーピー」鳴り始めます(笑)。
このアラートが鳴るタイミングと、自分の頭の「ぼーっ」と感がリンクしてるんですよね。「あ、やっぱり今、脳に酸素足りてないんだ」と。
なので私は、打ち合わせ中でも定期的に窓を開けたり、サーキュレーターを回して空気の循環を意識しています。ミーティング中はアラート音がうるさいので電源を抜くこともありますが、終わったらすぐに再設置しています。
リアルな“現場の痛み”:酸素不足の場所で起こること
例えば、昔よく行っていた某家具量販店のビル。3回中3回、なぜか体がだるくなるんです。最初は気のせいかと思いましたが、あそこ、おそらく換気が足りてないんだろうなと。
同じような体験、ありませんか?
- 人が多い会議室で、急に眠くなる
- 満員電車で頭が回らない
- 換気の悪い場所で「集中できない」と感じる
こういうの、全部「CO2過多」=「酸素不足」かもしれません。
ツール紹介:CO2計測器は1万円以下で導入可能
「CO2計測器って高いんじゃない?」と思われるかもしれません。
ですが、Amazonなどで探すと、1万円以下でUSB充電式のコンパクトモデルが手に入ります。
導入のハードルが低い理由
- 工事不要、ポンと置くだけ
- デジタル表示で一目瞭然
- アラート機能付き
「数値化」することで、感覚ではなく“仕組み”で動けるようになるのが最大のメリットです。
環境設計としての「酸素マネジメント」
ビジネスに応用するなら、「集中力を高める設計」の一部として考えるのが良いと思います。
よく「気合いで乗り切る」とか言いますけど、体が整ってなければ無理なんですよね(笑)。
環境が変われば、パフォーマンスは変わります。CO2計測器はその“変化の気づき”を与えてくれる装置。リモートワーカーや在宅ワークが増える中、自宅の環境が最適かどうかを“見える化”する一歩になるかもしれません。
また、CO2計測器による環境データをログとして記録し、自身の集中力や作業効率と照らし合わせることで、パフォーマンスの波の“見える化”も可能です。環境とパフォーマンスの関係性を記録していくと、意外な傾向が見えてくるかもしれません。
CO2と集中力データは、AIで“習慣改善”に活かせる
最近では、CO₂センサーとAIを連携させて、「集中力が落ちやすい時間帯」や「空気環境の傾向」を自動で分析する仕組みも実現しつつあります。
たとえば──
- CO2濃度のログと作業記録を組み合わせて、パフォーマンスの波を可視化する
- AIが「集中力が落ちやすい環境条件」を学習して、リマインドや換気タイミングを自動提案する
- 将来的には、バイタルデータとも連携し、“個別最適な空間設計”を実現する
そんな未来も、決して遠くないかもしれません。
私たちの体調や集中力の揺れを“なんとなくの感覚”で終わらせず、AIの視点でデータ化・習慣化することは、これからの働き方にとって非常に価値あるアプローチだと思います。
【まとめ】あなたの“集中力低下”、もしかして空気のせいかも?
もちろん、集中できない理由は他にもあります。たとえば、「昼食後の眠気」は、血糖値の急上昇(血糖値スパイク)が原因であることも。特に、GI値(グリセミックインデックス)が高い食品、つまり精製された炭水化物を摂取した場合には、血糖値が急上昇したあと急降下することで、強い眠気が襲ってきます。
この“血糖値スパイク”の影響についても、実は私はかなり深掘りしているテーマです。血糖値と集中力・感情コントロールの関係性については、また別の記事でしっかり取り上げたいと思います。ぜひそちらも楽しみにしていてください。
まずは「酸素」。見えないからこそ、盲点になりがち。でも、“集中できない”にはちゃんと理由があるんです。
もし在宅ワークや会議中に「なんかボーッとするな」と感じたら、まず空気の状態を疑ってみてください。
「酸素を整える」という視点、意外とビジネスに効いてきますよ。
FAQ(よくある質問とその答え)
- Q1. CO2計測器って、本当に必要ですか?
A. 必須ではありませんが、仕事効率や集中力の改善を「見える化」できるため、特に在宅ワーカーにはおすすめです。 - Q2. どのくらいの頻度で換気すれば良いですか?
A. CO2濃度が1000ppmを超えたら換気のサイン。30分〜1時間に一度、数分の換気でも大きく改善されます。 - Q3. 普段の仕事場に置く場所のおすすめは?
A. 自分の顔の高さに近い位置(机の上など)が理想です。CO2は空気中に拡散するため、部屋全体の平均値を反映します。 - Q4. 他に集中力を妨げる環境要因はありますか?
A. 光量不足、騒音、温度・湿度の不快感、座りすぎなども影響します。CO2濃度と合わせて見直すと効果的です。 - Q5. 高機能なCO2センサーと安価なモデル、どう違う?
A. 測定の精度や反応速度、付属機能(アプリ連携など)が異なりますが、まずは安価モデルで十分です。習慣化が大事。
いますぐできる小さな見直しから
「空気の質で集中力が変わる」ということを、もし少しでも実感されたなら──行動に移すことが何よりの第一歩です。ここでは、日常の中で誰でも取り組める“空気と集中の整え方”を5つご紹介します。どれも特別な知識や道具を必要としないものばかりです。小さな工夫が、大きな違いを生むかもしれません。
- CO2計測器の定期的な設置・運用を継続する
- ミーティング時の換気ルールを明確化する
- 血糖値と集中力の関係について別テーマでブログ執筆
- 在宅ワーク環境のCO2・酸素濃度のデータログ取得を検討する
- AIによる酸素・CO2濃度と集中力の関係性の補足情報を追加する
もっと深く知りたい方へ
「うちの環境も、ちょっと見直した方がいいかも?」と思った方は、いつでもセレンデックまでお気軽にご相談ください。
他にも、集中力や働き方に関する気づきが詰まった記事をたくさん公開しています。よかったら、ぜひそちらも読んでみてくださいね。
この気づきが、どなたかの日常にちょっとしたヒントを届けられたなら嬉しいです。