こんにちは。
AIと人間の違いとして、「AIは眠くなることがない、そして感情的になることがない」でも人間には感情がありそれが超重要、と深夜に記事作成をしながらしみじみと感じている、株式会社セレンデック代表の楠本です。
最近、あるクライアントとの打ち合わせで、ふとこんな質問が出ました。
…正直、ドキッとしました(笑)。
でも、これ、かなり本質的な問いなんですよね。
なぜなら、今のWeb制作現場って、“人がやる理由”が曖昧になってきているからです。
生成AIが「構成」「デザイン案」「キャッチコピー」まで出してくれる。だからこそ、ディレクターがただの“指示出し役”や“タスク管理者”であるなら、たしかに「AIで代替できるかも」と思われても不思議じゃありません。
でも、僕自身この1年、生成AIと向き合いながら、現場で「本当に変わったな」と感じていることがあります。
それは──
ディレクターの価値が“見えにくく”なったけれど、“重要性”はむしろ増しているという事実。
今回はそんな「制作フローの裏側」で起きている変化と、これからのWebディレクター像について、リアルな視点で掘り下げてみたいと思います。
気づけば変わっていた「ディレクターの日常業務」
生成AI導入前の制作フローと役割分担とは?
以前のWeb制作では、ディレクターがワイヤーフレームを描き、デザイナーがビジュアルを作り、エンジニアがコーディングする…という分業が基本でした。
とにかくタスクが多く、スプレッドシートやチャットでの調整に追われ、“手が足りないから忙しい”状態が常態化していた。
僕自身、「スケジュールを間に合わせること」ばかりが頭にあって、戦略や本質的な価値を考える余裕なんて正直なかったです。
でも、そんな中に生成AIが入ってきた。
- 構成案はChatGPTに聞けば一瞬、
- FigmaにはAIアシスト、
- 画像生成もできる。
「これはラクになるぞ」と思ったのですが…
生成AIが入って「一部自動化」された瞬間
たしかに、初稿や構成の“たたき”は早くなりました。
でも、逆に「この出力、使えるの?」「どこから人が見る?」という“判断の壁”が新たに現れたんですよね。
AIが出してくれた案を“そのまま通す”わけにはいかない。
逆に、人間が介在する意味──“取捨選択と編集の力”がより求められるようになった。
つまり、「ラクになる」どころか、「求められる思考の質」はむしろ上がったんです。
「AIに任せればOK」じゃなかった?──ズレる期待と現実
実際の制作現場で起きた混乱とは
ある案件で、構成出しをとある新人スタッフと一緒にやってみたんです。
ChatGPTに指示を入れて構成案を出したところ、彼女はこう言いました。
「え、これでOKじゃないんですか?」
…悪くない。でも、顧客のトーンや目的、競合との違いまでは加味されていない。
つまり、「正解っぽいもの」は出せるけど、「その企業にフィットした答え」は出せないんですよね。
ここで止まってしまう若手が増えているのは、「AIの出力が“正解”と思ってしまう」から。
そのままコピペしても、フィードバックで戻される。
結果、「AIがあればいいんじゃ?」という誤解が生まれてしまう。
必要になったのは“設計力”と“判断軸”
じゃあ、何が必要なのか?
それは、AIの出力を「文脈に合わせて翻訳・調整する力」です。
どこまでがAIに任せられるか?
どこからが“人”が見るべきポイントか?
この“判断の設計”がないまま進めると、制作がブレるし、関係者も混乱する。
つまり、「AIが出した案を、どう扱うか」を設計する人間の力=ディレクターの新しい役割なんです。
生成AIと組んで「強くなった人」の共通点
問いを立てられる人は、AIを“部下”にできる
あるベテランの女性ディレクターは、AIに指示を出すときに「この商品の“違和感ポイント”から提案して」と言ってました。
──視点が鋭い。
彼女は「正解を求める」のではなく、「問いの深さ」を重視している。
だから、AIからの出力も“考える素材”として扱える。
AIは“質問の質”で答えの質が変わる。
これは、「問いを設計できる人=AIを使いこなせる人」という意味でもある。
逆に、迷い続ける人の特徴とは?
一方で、ずっと悩み続けてしまう人もいます。
それは「どれが正解?」とAIに“委ねて”しまうタイプ。
AIの出力に依存しすぎると、かえって判断に迷いが出て、動けなくなる。
つまり、AIは便利だけど、使い方を決めるのは人間。そこを担うのがディレクターの本質です。
「自分にできるのか?」と思った方へ伝えたいこと
ビジネス経験や子育て経験は、ディレクションの強みになる
最近、主婦の方や異業種からの転職希望者と話す機会が増えました。
中には「コードもデザインもできませんけど…」と不安そうな方もいます。
でも、調整力・傾聴力・タスク管理…これって、ディレクションに不可欠なスキルなんですよね。
むしろ、「技術に詳しくないからこそ、ユーザー視点で見られる」という強みもある。
プログラミングやデザインができなくても、“人とAIをつなぐハブ役”としてのディレクターというキャリアは、今まさに可能性が広がっています。
「AI時代のディレクター=人間らしさの通訳者」
生成AIが進化すればするほど、最後に必要なのは“人の感性”。
たとえば、
- 顧客のちょっとした表情の変化
- 社内メンバーの疲れ具合
- 曖昧なフィードバックのニュアンス
こういう“ノイズ”を拾って翻訳し、形にするのは、AIでは難しい。
だから、僕はこう思っています。
「AI時代のWebディレクターは、“人間らしさの通訳者”である」
これは、技術職ではなく“感性と知性の職業”なのかもしれません。
まとめ──「AI×人間」の時代、選ぶのはあなた
生成AIによって、Web制作の現場は大きく変わりました。
たしかに、従来型のディレクター像は“過去のもの”になるかもしれません。
でも、その先にあるのは、
「人にしかできないこと」の価値が増す時代だということ。
そして、それは必ずしも“高度な技術者”でなくてもいい。
- ビジネス経験者
- 子育て中の主婦
- デザインスクール卒業生
…どんな背景の人でも、「AIを使って何をしたいか」があれば、ディレクションは目指せます。
もし「自分にもできるかも?」と思ったら、まずは一歩踏み出してみてください。
セレンデックではAIウェブディレクター育成講座を開催しています。ご興味ある方は是非ご参加ください。体験会、説明会も実施しています。
—AIを実務で活用するための講座
「じゃあ、どうやってその力を身につけるのか?」
「現場で、AIをどんな風に使えばいいのか?」
そうした問いにお応えする形で、AIを実務で活用するための2つの講座を運営しています。
🎓 AIディレクター育成講座(個人向け)
「言語化」「問いの設計」「アウトプット改善力」を体系的に学べるオンライン講座。未経験からでも“使いこなせる人”になるための実践ノウハウを凝縮。
セレンデックではAIウェブディレクター育成講座を開催しています。ご興味ある方は是非ご参加ください。体験会、説明会も実施しています。
👉 AI Webディレクター養成講座はこちら
🏢 AIDX法人講座(企業研修向け)
中小企業の現場で成果を出すための、AI内製化&チーム導入支援プログラム。実際の業務課題を教材に、チーム単位でAI活用を浸透させていきます。
それでは、また次回の記事でお会いしましょう。AIを活用して仕事するのは楽しいですね。










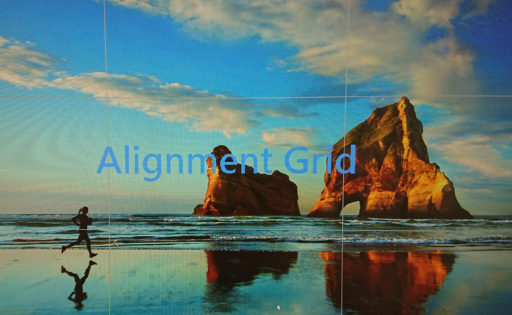





「Webディレクターって、生成AI時代にも必要なんですか?」