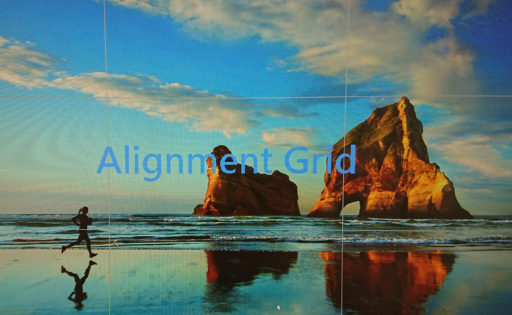解説YouTube動画はこちら 仕事が取れないWEBデザイナーの現実
こんにちは。「Webデザインの実績がないのは、実績がないという“実績”があるからで、Webデザイン制作の実績があれば、実績は作れるんですよ」、と進次郎さんも応援してくれると信じている、株式会社セレンデック代表の楠本です。
「スクールを出て、ポートフォリオも作った。でも、応募しても全然通らない…」
「未経験OKの案件に送っても、返事すらこない…」
そんな経験、ありませんか?
その原因、もしかしたら“スキル不足”ではないのかもしれません。
実はあなた、知らず知らずのうちに“実績ループ”にハマっているのかもしれません。
今回は、Webデザイナーが陥りがちな「実績がないから仕事が取れない → 仕事が取れないから実績が作れない」ループの正体と、そこから抜け出すための具体的な視点と行動についてお話します。
焦って受けた“無料案件”や、“テンプレだけのポートフォリオ”では、選ばれません。
でも、工夫次第で「実績がなくても信頼される人」にはなれます。それができるのが、**提案力・設計力を備えた“Webディレクター型デザイナー”**という視座です。
このあと、具体的に掘り下げていきます。
「実績がないと仕事が取れない」──このループ、経験ありませんか?
「未経験OK」なのに実際は実績重視される現実
「未経験歓迎!」と書かれているのに、実際に応募すると競合が全員“実績あり”──この構造、冷静に考えると当然かもしれません。
発注側の視点に立てば、実績がある人にお願いしたくなるのは自然なこと。いくら「未経験OK」とあっても、“より安心できる人”を選ぶのは、コストと時間を無駄にしたくないという心理があるからです。
架空ポートフォリオでは信用されない理由
「こんな保育園サイトを作りました」「レストランのLPを作成しました」
── 一見プロっぽいweb制作実績、ポートフォリオ。でも、実は講座の課題で作った“架空サイト”だったり、テンプレートをアレンジしただけだったり。
発注者からすると、それが実際に公開されているのか、実務で求められるレベルなのか、見分けがつきません。最近では、ポートフォリオ自体が“有料講座の使い回し”であることも増えており、「この人の実力がどこまで本物か?」が判断しにくくなっています。
結果的に、ポートフォリオだけでは信用されにくくなっている現実があります。
焦って受けた無料・激安案件が“使えない実績”になるリスク
「とにかく実績を作らなきゃ!」と焦って、無料や激安案件に飛びつく──これもよくあるパターンです。
ですが、発注者の目的が「安くやってくれる人を探す」だけの場合、成果物の質や、レビューの協力といった“次に繋がる要素”が得られないこともあります。
その案件、実績として“使える”でしょうか? 作って終わり、掲載も不可、レビューもなし──だとしたら、それは“実績”ではなく“作業”かもしれません。
“実績ループ”が起きる構造を整理してみる
「安心感」を買う発注者心理とクラウドソーシングの構造
発注者が求めているのは、成果物そのもの以上に「この人に任せても大丈夫か」という“安心感”です。
クラウドソーシングなどでの案件獲得は、スキル以上に“実績・評価・レビュー”が重視される仕組みになっています。つまり、最初の0→1をどう突破するかが鍵になります。
テンプレート時代の“見分けづらい”ポートフォリオ事情
WordPressテーマやCanvaなどの登場により、非デザイナーでもそれっぽいサイトが簡単に作れる時代になりました。
その結果、発注者からすると「これは本当にこの人が作ったのか?」という疑念が生まれやすくなっています。見た目の美しさより、「どう作ったか」「なぜその構成にしたのか」といったプロセスの説明が重要視されるようになってきています。
「なぜ選ばれないのか?」の視点がないと繰り返す
「実績がないから選ばれない」──確かにそうです。
でも、「じゃあ、どんな実績なら選ばれるのか?」という視点が抜け落ちている人が多いのも事実。選ばれない理由を、自分の“実力不足”だけで片付けずに、「発注者が何を求めているか?」に立ち返る必要があります。
Webデザイナー初心者が「実績を作る」ための最初の戦略
無料・激安案件でも「レビュー・実績公開OK」を前提に交渉する
実績を作るために無料や激安で請け負うことは、一つの戦略です。
ただし、「レビューをもらう」「実績として掲載OK」という条件を、事前にしっかり交渉しておくことが大前提です。安く受ける代わりに、“信用につながる要素”を確保する。これが“未来への投資”の考え方です。
「ちゃんとした案件を選ぶ」ことで時間を無駄にしない
「安くても、しっかり使える実績になる案件を選ぶ」──ここが大切なポイントです。
例えば以下のような条件を基準にすると判断しやすくなります:
- 実際に公開される予定の案件か?(例:実店舗のホームページ制作)
- 成果物をポートフォリオに掲載してOKか?
- ツールや作業内容が自分の得意分野と合っているか?
- コミュニケーションがスムーズで、信頼できる依頼主か?
- レビューをもらえる可能性があるか?
これらの条件を満たしていれば、たとえ報酬が低くても、結果的に“次につながる実績”になります。逆に、ただ作業量だけ多く、成果も公開不可、レビューももらえない案件は「時間を奪うだけの案件」になりかねません。安く受けるからこそ、“目的のために選ぶ力”が必要なのです。
成果よりも“お客様の声”が次の信用に繋がる
レビュー、つまり「この人にお願いして良かった」という“お客様の声”は、何よりの信頼材料です。
単なる成果物よりも、そのプロセスでどれだけ丁寧に対応したか、納期を守ったか、修正に応じたか…そうした“人としての信頼”が次の案件獲得につながります。
ポートフォリオで選ばれるための“実績の見せ方”と差別化の視点
「何を作ったか」ではなく「なぜ、どう作ったか」を語れるか
単に「飲食店のホームページを作りました」と言うだけでは、他の応募者との差別化は難しい時代になっています。
それよりも大事なのは、「どんな課題を解決するためにこの構成にしたのか」「なぜこのデザインを選んだのか」という“思考のプロセス”を語れることです。これはいわば、デザインの「裏側」にあるストーリー。これが語れると、「この人はちゃんと考えている」「任せても大丈夫そう」と発注者に感じてもらえるのです。
ちょっとしたテキストや構成の工夫にも、理由があるはずです。自分の中でその根拠を持っておくこと。それを言語化できるようになると、格段に信頼度が上がります。
「この要望にこう応えた」というプロセスが強みになる
「ヒアリングしてみたら、実は“スマホで見やすく”が一番大事な条件だった」
「問い合わせ数が伸びないのが悩みだったので、CTA(Call to Action:行動喚起)ボタンを目立たせるようにした」
──こうした“お客様の要望”に対して、どう考え、どう対応したかのプロセスは、実は最大のアピールポイントです。制作物という「結果」だけでなく、そこに至る「プロセス=思考と工夫」をセットで伝えること。それこそが、初心者と“選ばれるデザイナー”の分かれ道になります。
「提案・設計・構成」の視点を最初から含める
「言われた通りに作る」だけでは、これからの時代のWebデザイナーとしては厳しいかもしれません。
特に中小企業では、「何をどう作ったらいいか分からない」というところから相談されることも多いため、提案・設計・構成まで視野に入れて動ける人が重宝されます。これはつまり「ディレクション思考」です。
- 何を目的にしたサイトなのか?
- ユーザーにどんな行動をしてもらいたいのか?
- 情報設計や導線設計は適切か?
…こうした視点を持って制作に入ることで、「単なる外注」から「信頼できるパートナー」へとポジションが変わっていきます。このディレクション思考は、単なる技術力以上にクライアントのビジネスの成功に貢献する重要なスキルです。プロジェクトの全体像を理解し、目的達成に向けた最適な解決策を提案できるデザイナーは、長期的な信頼関係を築くことができるでしょう。クライアントとの密なコミュニケーションを通じて、潜在的な課題を発見し、それを解決する提案を行うことで、あなたの価値は飛躍的に高まります。
中小企業案件で“信頼されるWebデザイナー”になる方法と実践スキル
ドメイン・サーバー・メールなどの周辺知識が“頼られる理由”になる
これは現場の実感でもありますが──中小企業の方々からは、「とにかく全部まかせたい」というニーズがとても多いんです。
たとえば、
- ドメインの取得(例:お店の名前.com)
- サーバー契約と初期設定(例:Xserverやさくらなど)
- DNS設定やSSL化(セキュリティ対応)
- メールアドレスの作成と設定(例:info@〜)
こういった作業まで対応できると、それだけで「この人、頼れるな」と思ってもらえる確率が格段に上がります。特に中小企業では、社内にWeb担当者がいないケースが多く、「誰かに丸ごと任せたい」というニーズが非常にリアルに存在しています。ツールや手順はググれば出てきますし、ChatGPTなどのAIを活用すればサポートも簡単に得られる時代です。知識ゼロでも“やりながら覚える”ことは十分可能です。この周辺知識は、あなたのサービスをより包括的なものにし、競合との差別化を図る大きな武器となります。クライアントにとってのワンストップサービスを提供することで、あなたの存在価値はさらに向上します。
「全部まかせたい」と思われる人になる
デザインだけじゃない。“相談できる人”になる──これが大きな差別化になります。
たとえば、
- サイト構成を提案する
- 文章の修正も代行する
- 写真の撮影アドバイスや、素材選定まで一緒に考える
など、周辺領域まで少しずつ対応できるようになると、「全部まかせたいんだけど」と言ってもらえる機会が増えていきます。もちろん、すべてを自分一人で完璧にやる必要はありません。外部ツールを使ったり、知人に協力を仰いでもOK。大切なのは、「どうしたらこの依頼主が助かるか?」を一緒に考え、解決に向けて伴走する姿勢です。
CanvaやAIを使った“実務に活かせるスキル”の提示
最近では、Canvaなどのノーコードツールや、ChatGPTのような生成AIも、十分に実務で活用されています。
- Canvaでバナーを量産して提案
- ChatGPTでキャッチコピーの案出しや構成案をサポート
- Notionで納品後の「使い方マニュアル」を作成
など、いわゆる“デザイン”の枠を超えたアプローチができると、発注者からの評価も変わってきます。特に、「デザインは得意だけどライティングは苦手…」という方には、AIの補助が心強い味方になります。「ツールを使える」ではなく、「ツールでお客様の目的を実現できる」が重要です。これもまた、“選ばれる理由”になります。
まとめ:マーケティングと同じ。自分を売る設計とポジショニングを持とう
「実績がないから仕事が取れない」──この“実績ループ”は、確かに厄介です。
でも実は、抜け出す方法がないわけではありません。むしろ重要なのは、「どんな実績が信頼につながるのか?」を戦略的に考えること。
実績=ただの制作物ではなく、“信頼の証拠”です。その信頼を得るために、私たちは「誰に、どんな価値を、どう届けたいのか」を言語化しておく必要があります。これってまさに、マーケティングの世界で言うポジショニングなんですよね。
「自分の実力・実績で誰に選ばれるか」を分析する
例えば、
- 「小さな店舗のオーナーと直接やり取りできるのが得意」
- 「テンプレート活用が得意だから、スピード重視の人向け」
- 「文章構成にも強いので、ライティング含めた提案ができる」
──こんなふうに、自分のスキルや性格をベースにした“ポジション取り”があるだけで、仕事の取り方は大きく変わります。選ばれるには、まず「自分で自分をどう売るか」を決めておく必要があるのです。
会社員的「やった分だけ報酬」思考からの脱却
フリーランスは、時間=お金ではありません。
たくさん動いても、収入ゼロのときもあります。逆に、一つの提案で一気に信頼され、継続案件が続くこともあります。だからこそ「いま頑張ってもすぐには成果にならない」ことに耐えられるか──それが、脱・実績ループにおいて最も大事なマインドセットです。
「今は投資」だと割り切れる人が、長く信頼される
初期の実績づくりは、利益が出ないどころか“赤字”になることさえあります。
でも、それでいいんです。むしろ、そこにしっかり時間と労力を投じた人が、のちに「仕事を選べる」側になっていきます。急がば回れ──これは、フリーランスの基本です。「未来の自分への投資」だと割り切って、いまの努力を重ねていきましょう。
まあ・・どんなことも最初が一番大変なので頑張っていきましょう!
セレンデックではAIウェブディレクター育成講座を開催しています。ご興味ある方は是非ご参加ください。体験会、説明会も実施しています。
よくある質問(FAQ)
- Q1. 無料や激安で案件を受けるのって、結局“安売り”になるのでは?
A. 安売りではなく“初期投資”と捉えることが大切です。
ただし、「レビューや実績公開が条件」「ポートフォリオに載せられる内容に限る」といった“戦略的な受け方”をしましょう。闇雲なボランティアではなく、目的を明確にした“未来の信用への投資”です。 - Q2. 架空のポートフォリオしかないけど、仕事は本当に取れますか?
A. 取れないわけではありませんが、信頼を得るのが難しいのが現実です。
「なぜこの構成にしたのか?」「どう考えて作ったのか?」など、プロセスを丁寧に言語化することで差をつけることは可能です。ですが、やはりリアルな案件での実績が1件あると、その後の信頼度は桁違いに上がります。 - Q3. 実力が足りていない気がして、自信が持てません…。
A. 完璧な状態になるのを待っていては、いつまでも動けません。
むしろ「いまの実力で、どこまでできるか」を知るためにも、小さくてもいいのでリアル案件に関わってみることをおすすめします。学びながら改善し、フィードバックを受けながらスキルを磨いていく…それが一番の近道です。 - Q4. クラウドソーシングで応募しても、まったく通りません。
A. 多くの人が同じ壁にぶつかります。
理由の多くは「他の応募者と差別化できていない」ことと、「信頼材料(実績・レビュー)が足りない」こと。
最初の1件は、クラウドソーシング外で知人や地域の事業者など“つながりのある場所”で探す方が成功確率が高く、次につながる実績になります。 - Q5. Webデザイン以外のことも頼まれそうで不安です…。
A. その不安こそが、実はチャンスです。
中小企業では「全部まとめて任せたい」というニーズが多いため、ドメイン取得・サーバー設定・メール設定など、基本的な周辺知識を少しずつ身につけておくことで“頼られる存在”になれます。
わからないことがあっても、AIや先人の情報を活用すれば必ず乗り越えられます。 - Q6. CanvaやChatGPTを使ってもいいんですか?
A. むしろ積極的に使ってください。
いまの現場では、CanvaやChatGPTなどのノーコード・AIツールが大きな武器になります。
重要なのは「道具を使ってどう価値を出すか」であり、「ツールの使用=手抜き」ではありません。お客様の目的を叶えるためなら、どんな手段も正解です。 - Q7. 「自分を売る」と言われても、どうしても苦手です…。
A. 誰かに“売り込む”というより、「こんな人なら頼みたい」と思ってもらえる準備をすることが第一歩です。
そのために必要なのが「実績づくり」と「自分の強みの棚卸し」。無理に自分を大きく見せる必要はありません。「これまでこういうことを考えて、こう動きました」と“事実ベース”で伝えるだけでも、立派なセルフブランディングです。