🌟 導入:企画書作成も“全部AIまかせ”はまだ早い
こんにちは。AI業務設計士、株式会社セレンデック代表の楠本です。
先日、ある中小企業の経営者様からこう聞かれました。
その気持ち、よく分かります。でも、現実問題、今のAIは“全部完璧”には対応しきれていません。
むしろ「企画書作成も工程分けが肝」で、それがうまくやれると、驚くくらいラクにも、質も高くもなるんです。(いずれは一言でできるようになるかもですけどね)
YouTube関連解説動画はこちら
🤔 「全部任せたら、成果も全部丸投げ?」
たとえば、「動画を1本作ってほしい」「企画書を作ってほしい」という依頼。
その裏側には、次のような複数の工程があります。
- 情報収集
- 台本または構成作成
- 原稿執筆や要約
- 音声合成/デザイン調整
- 編集・出力
「AIができる」と言われる領域でも、これらすべてを1ツールで完結することは難しい。
「どう分けて、どこを誰に任せるか?」──ここが大事なんです。
🙋♀️ よくある“ユーザーの声”と現実のギャップ
ツール多すぎて、どれ使えばいいかわかりません…。
正直、最初は誰でもそうです。今は“専門特化型AI”が乱立していて、得意なこと・不得意なことが明確に分かれています。
たとえば、こうした「馴染みあるAI」で工程ごとに最適化していくのがコツです。
- 情報整理・リサーチにはPerplexity(パープレキシティ)やGemini(ジェミニ)
- 構成案のたたき台にはChatGPTやClaude(クロード)
- 文章全体の流れや言い回しの推敲はChatGPTやClaude,Gemeni
- 図解・レイアウト調整にはCanvaやGamma(ガンマ)、Genspark
試してみたけど、イマイチでした…。
そのツールが“悪い”わけではなく、「工程の設計」がズレていた可能性があります。
以前、ある製造業のクライアントが「AIに企画書を作らせたけど、全然ダメで」と落胆されていました。でも話を聞くと、設計意図も背景情報も与えずに出力させていたんです。
そこで工程を4段階に分けて、この流れに変えたら、「実務で使える企画書になった」と大きく変化しました。
- Perplexityで市場情報と一次データを収集
- ChatGPTで構成アウトラインを設計
- Claudeで文体と説得力の調整
- Genspark,CanvaやGammaで図解・資料デザインを整える
🛠 実践・対処法:AI仕事の“分業設計”フロー
私たちが実際に取り組んでいるのは、次のようなステップです。
1. 業務を分解し、工程ごとに切り出す
たとえば企画書作成なら、以下のような工程に分けられます:
- 企画・リサーチ:Perplexity、Gemini、Claude
- 構成・台本:ChatGPT、Claude
- 文章推敲:Claude
- デザイン・レイアウト:Canva、Gamma
ここまで整理することで、「どのツールが、どの工程に強いか」が見えてきます。
2. ツールの選定基準を明確にする
ツールを選ぶときは、次の4つの軸で評価します:
- 精度・出力品質
- 使いやすさ(UI/UX・操作性)
- 他ツールとの連携性
- ランニングコスト
現場メンバーが触れる前提で選ぶことが、継続活用のポイントです。
3. 小さく試して、改善する
いきなりフルセットで回すのではなく、まずは1つの工程だけ試してみる。
たとえば「まずは構成だけAIに任せてみよう」と始めて、次の観点で、定量と定性の両面から振り返っていきます。
- どのくらい時間短縮できたか?
- 精度やアウトプットはどうか?
- チーム内で運用できそうか?
💡 気づき・変化:「AI活用」は“道具選び”ではなく“設計力”の勝負
こうして分業設計を意識すると、次のような好循環が生まれます。
- 出力のばらつきが減る
- エラーややり直しが減る
- 担当ごとの引き継ぎもスムーズになる
実はこのステップ、AIに限らず、人の仕事にも通じるんですよね。
得意な人に得意なタスクを割り振っていく。
それと同じように、AIにも「この工程はこの子が得意」と理解し、任せていくことが大事です。
つまり、“設計する力”が問われているわけです。
✨ まとめ:「魔法のツール」ではなく「設計の工夫」で成果が決まる
- AIは現時点では“万能”ではなく“特化型”が主流
- 業務を分割して、最適なツールを当てはめる設計が必要
- 設計こそが成果の精度とスピードを左右する
「AI任せにしたらラクできる」は、ちょっとだけ早とちり。実際は、「どこを、どう任せるか?」を考える力が求められている。
でもそれは、誰にでも身につけられるスキルです。
「最初はうまくいかなくて当たり前。そこから少しずつ精度を高めていく」──このプロセスに寄り添うのが、私たちの役割でもあります。
この設計視点、もっと掘り下げたい方は、ワークショップや業務設計セッションも可能です。ご興味ある方は、お気軽にご相談くださいね。
AIツールはたくさんありますから、仕方ないです
むしろ、「迷ってるからこそ、前に進める」んです。
一緒に考えていきましょう!!




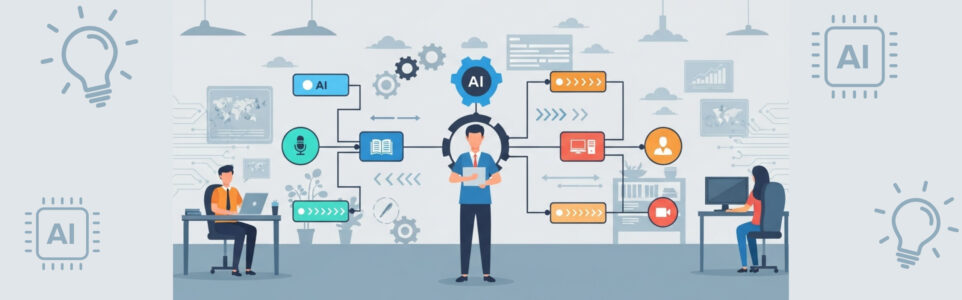











うち、企画書をAIに“全自動で”作ってほしいんですけど…