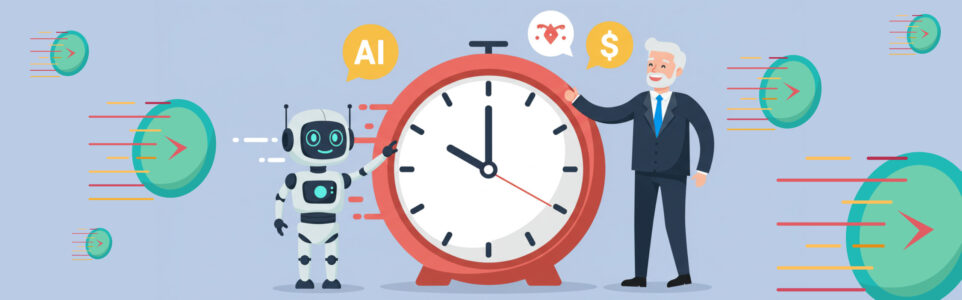はじめに:「この作業、2時間かかります」と言われたら?
こんにちは。セレンデック代表の楠本です。AIが面白すぎて毎日いじり倒しています。
最近、ある中小企業の経営者と話していた時のこと。「外注さんが“2時間かかる作業”って言うから、それくらいかかるものだと思ってたんですよ」と。
でも、その作業内容を聞いてみると、ChatGPTを使えば10分で終わる内容だったんですよね。
──これ、決して他人事ではありません。
AIリテラシーがないと、知らない間に“損する経営”をしている。
今日はそんなリアルな話を、体験ベースでお伝えしていきます。
なぜ「AIリテラシー」が経営者にとって必須なのか?
よくある誤解があります。
「AIは現場で使えばいい」
「経営者が詳しくなくても、実務が回ればOK」
──本当にそうでしょうか?
結論から言います。
経営者こそ、AIを理解していないと損します。そしてその“損”は、見えないまま静かに積み上がるんです。
「AIを知らない経営者」がリアルに損をするシーン
① 外注費が適正かどうか判断できない
冒頭の例のように、「2時間かかります」と言われた作業が、実はAIを使えば10分で終わるケースが増えています。
でも、AIを知らないと──「そうなんですね、お疲れさまです」で、旧来の工数感で支払ってしまう。
これ、悪意がなくても“情報の非対称性”で損してます。
② 社内の工数感とズレる
スタッフが「このレポート作成、大変でした」と言ってきたとします。
でも、AIならテンプレ生成+要約で30分で終わる内容かもしれない。
経営者がAIに無知だと、その判断がつかないんです。
「よく頑張ったね」と褒めながら、本当は“時間の使い方が間違っていた”という事態が、日常的に発生してしまうんですよね。
③ 「業務設計」そのものが古いまま
同じ作業をずっと人力でやっている
業務フローが前提のままツールだけ変えている
評価制度が“時間をかけた人が偉い”になっている
こういった「前提のズレ」こそが、会社の競争力をじわじわ削っていくんです。
私は、AIに「100万円以上」と「500時間」ぶち込みました(笑)
偉そうなことを言っていますが、私も最初は手探りでした。
ただ──丸投げは一切していません。
むしろ、最初から自分でリサーチして、検証して、使い倒しました。
- ChatGPTにプロンプトを試しまくる
- プロンプトの微妙に変えて検証、パターンをまとめ、精度の違いを検証
- 業務ごとにどこまで使えるかを社内フローで試行
気づけば、100万円以上の有料ツールやAPIを試し、500時間以上はAIに“ぶち込んで”ました(笑)
そして分かった。「AI時代の経営は“再設計”が前提」
ここからが本題です。
AIの導入って、「便利なツールを導入する」という感覚ではダメなんです。
そもそも、業務全体・評価制度・報酬設計まで再設計しないと機能しません。
再設計が必要なもの一例:
| 項目 | 見直す視点 |
|---|---|
| 業務フロー | AIに任せられる工程の自動化と再配分 |
| 役割分担 | 人がやるべき“創造的工程”への集中 |
| 評価制度 | 「かけた時間」ではなく「成果・工夫」で評価 |
| 外注契約 | 工数ではなく“成果物”ベースでの報酬構造 |
| 教育 | スタッフのAI活用スキル育成も含めた設計 |
AIをベースにした経営設計を行わないと、せっかくのAI投資が“無駄な便利グッズ”止まりになります。
情弱は搾取される時代へ──冗談抜きで、経営の明暗が分かれる
ちょっと強めに言いますが、これ本気で大事です。
AIを知らない=情報弱者。
情報弱者は、搾取される。
- 無駄な外注費
- 無駄な社内工数
- 無駄なツール導入
- 無駄な教育投資
…全部、「知らないこと」が原因です。
しかも厄介なのは、それに気づかないまま“なんとなく経営がしんどい”と感じてしまうこと。
AIに関して、今後は「無知=リスク」であることを強く意識すべきです。
とはいえ「技術者になれ」とは言ってません(笑)
ここで誤解されたくないのは、私は別に「Pythonを学んでください」とか、「LLMの仕組みを理解しましょう」と言ってるわけじゃないんです。(LLMの大前提は理解しておいた方が本当はよいですけどね 笑)
経営者として、“どこにAIを使うか”を設計する視点が必要だということ。
- 「業務のどの部分に使うか」
- 「AIが出した結果をどう判断するか」
- 「スタッフにどう伝え、どう任せるか」
この視点を持っているかどうかが、これからの経営において“致命的な差”を生むと感じています。
まとめ:AIリテラシーは“判断力の質”に直結する
AIを理解するということは、「何を任せて、何を自分で考えるか」という、経営判断の軸を持つことだと思っています。
- どこで人が必要か?
- どこで自動化すべきか?
- どこに投資すべきか?
この判断を誤ると、人材の配置も、資金の配分も、まるごとズレていく。
でもAIを理解していれば、“使い方”だけでなく、“意味づけ”まで設計できるようになります。
最後に:まずは、自分で触ってみてください
「AIってなんだか難しそう」と感じている方。
まずはChatGPTでもGeminiでもなんでもよいのでAIに触れてみて、いま自分の業務で使えることを一つ探してみてください。
「社内の資料整理」でもいいですし、「採用の面接スクリプト作成」でもいい。
AIを“どのように活かしていくか”という視点が、経営者としての判断力を引き上げてくれます。
「誰かひとりでも、“もっともっとAIをやってみよう”、”理解しないとまずいな・・”と感じていただけたら幸いでございます」
— 株式会社セレンデック代表・楠本