こんにちは。人間の直感とAIの予測、どちらを信じますか? 株式会社セレンデック代表の楠本です。
最近、お客様から「AutoMLってどうなんですか?」「GPTと何が違うんですか?」と聞かれる機会が増えました。
正直、この問いが出てくる時点で、かなりアンテナ高いです(笑)
でも──その一方で、こういう声も多いんですよね。
うん、それ、めちゃくちゃわかります。
実は私自身も、最初は「AutoMLって“高そう”“難しそう”“大企業のものでしょ”」と思ってたひとりでした。
でも、いざ触ってみて──気づいたんです。
「これ、“中小企業こそ使える道具”じゃないか?」って。
今回の記事では、AutoMLの本質と、ChatGPTとの違い、そして「Googleスプレッドシートだけで始められるリアルな活用法」まで。
現場目線で、全部ぜんぶ、包み隠さずお伝えしますね。
「AutoML」ってそもそも何?──名前すら初耳な方へ
「オートエムエル…?何それ?ってところからなんですが」
──はい、それが普通です。AutoML(オートエムエル)とは、“自動機械学習”のこと。
簡単に言えば…
- AIに必要な「データの分析モデル」を自動でつくってくれる仕組み
- たとえば「売上予測」や「次に来そうなお客様予測」などを自動で作成
- 従来は専門家しかできなかった機械学習(ML)の工程を、誰でもできるようにしてくれる技術
→ 「難しい分析を自動でやってくれるAIの機能」と覚えてOKです。
そもそも論──AutoMLとGPTの違い、AIエージェントって?
「AutoMLとGPTって何が違うの?」「AIエージェントって最近よく聞くけど?」
このあたり、混乱して当然です。まずは地図を描くように、ざっくりと整理してみましょう。
| 種類 | GPT(生成AI) | AutoML | AIエージェント |
|---|---|---|---|
| 主な役割 | 言語処理 | 数値分析 | 自動実行 |
| 得意なこと | 質問応答、文章生成、要約 | 売上予測、顧客スコアリング、分類分析 | GPTやAutoMLを組み合わせて目的達成 |
| 具体例 | ChatGPT, Gemini | Google AutoML, dotData | AutoGPT, AgentOps |
→ GPTは“相談相手”、AutoMLは“分析屋”、エージェントは“マルチタスクな秘書”のようなイメージです。
「GPTに分析させればよくない?」──できること、できないこと
「CSVファイル読み込ませて、GPTに“売れ筋分析して”って言ったら済むんじゃ…?」
──これ、実は私も最初やってました(笑)
GPTでできること
- 小規模なCSVの要約、傾向抽出
- グラフの解釈、分析方針の提案
- フィルター・ピボットの設計サポート
つまり、「これって何が起きてるの?」みたいな“気づき”を得るには最高の相棒です。
でもGPTの限界
- 数値モデル(回帰式・特徴量設計)を“精度比較”して選ぶことはできない
- 結果の再現性が低い(同じ質問でも違う答えになりがち)
- 数理根拠が出せない(AUC、R2など)
要するに──
「なんとなく分かった気がするけど、それで月間施策を決めていいのか…?」
→ ちょっと心もとないですよね。
→ GPTは“仮説を立てる相談相手”には最適。でも“業務判断に使う予測モデル”はAutoMLの領域です。
「AutoMLってシステム?それともツール?」
実は──AutoMLは“機能”や“分析エンジン”であって、独立したシステムではありません。
- Google AutoMLは、ブラウザから使えるクラウド機能
- dotDataもGUI中心の分析ツールで、現場での内製化も可能
「導入=大がかりなシステム開発」ではないんです
→ Excelの延長線にある「道具」と考えてください。
BIツールとAUTO ML、何が違うの?──そもそもBIって何?
BIツールとは?
BI(Business Intelligence)ツールとは、企業内の様々なデータを“見やすく整理する”ツールです。
- 主に「過去の実績」「今の数字」を集計・可視化する
- よくあるのは“棒グラフ”“円グラフ”“ダッシュボード”など
AutoMLとの違い
| 比較項目 | BIツール | AutoML |
|---|---|---|
| 主な機能 | 過去の可視化(集計・グラフ) | 未来の予測(モデル構築) |
| 出力物 | 視覚化された結果 | 数理モデル・予測値・特徴量分析 |
| 目的 | 状況理解・報告 | 意思決定・業務改善 |
→ BIは“説明”、AutoMLは“判断材料”です。
第2部:AutoMLは“完璧な精度”じゃなく“動けるヒント”──小さな会社でも使える理由
「うちは小さい会社。データ30件でも意味あるの?」
「うち、顧客データ30件くらいしかないんですけど…意味あるんですかね?」
──これは本当に、よく聞きます。
でも結論から言えば、あります。充分あります。
ただし、「期待値の持ち方」と「やり方」を少し変える必要があるんです。
「100点の予測」ではなく「動けるヒント」を取る
AutoMLはたしかに、数千件〜数万件のデータがあると力を発揮します。
でも、30件〜100件でも「傾向」はつかめます。
- 勘よりはマシな判断ができる
- 特徴量(影響している項目)の“予想外な関係”に気づける
- 今後データを溜めていく方針の“方向性”が見える
これ、実際にやってみるとわかりますが、たとえ精度が60%でも、判断材料として十分に役立つんです。
データが少ない中小企業でも、まずは「動けるヒント」を得ることが重要です。
「IT化が進んでない」「紙ベース」でもできることはある
AutoML以前の課題として、「そもそもデータがない」というケースもよくあります。
でも、それでもやれることはあるんです。
手入力でも“まずはためる”ことから始まる
- ExcelやGoogleスプレッドシートで「毎日の売上」や「お客様の反応」を手で記録
- チャットやLINEの履歴を定期的にスプレッドシートにまとめる
- 紙のカルテや契約書から“最低限の項目”だけでも表にする
重要なのは、「AIを使うために記録する」という習慣を少しずつ入れること。完璧なデータではなく、まずは「使えるデータ」を蓄積することから始めましょう。
「1列追加」だけでAIに近づく
- 「次回来店あった/なかった」
- 「売上が前年比より上だった/下だった」
- 「トラブルがあった/なかった」
これらを“正解ラベル(目的変数)”として追加するだけで、AutoMLにとっては“学習できるデータ”になります。ほんの少しの手間が、未来の業務改善につながる第一歩です。
実際の業種別テンプレート活用例
ではここからは、よくある業種ごとに「実際どういう表がAIのタネになるか?」を紹介していきます。
✅ 美容業向け(施術履歴 → リピート確率)
- 顧客ID:C001
- 来店日:2024/08/01
- メニュー:カット
- 担当者:鈴木
- 単価:4,500円
- 所要時間:40分
- 来店間隔:30日
- 次回来店:あり
→ 「この条件の人は次回も来てくれる確率が高い」という予測が可能になります。
✅ 小売業向け(売上データ → 在庫最適化)
- 商品ID:A101
- 日付:2024/08/01
- 曜日:木曜
- 天気:晴れ
- 店舗:A店
- 売上数:12
- 在庫数:40
- 欠品発生:なし
→ 「金曜で雨だと売れにくい」などのパターンが見えてきます。
✅ Web制作・受託系(案件 → 炎上予兆検知)
- 案件ID:W001
- 業種:飲食
- 金額:40万
- 契約形態:一括
- 制作期間:14日
- 修正回数:2回
- トラブル発生:あり
→ 「業種×契約形態×修正回数」で“炎上リスクスコア”がつけられます。
このように、普段使っている表がそのままAIの土台になるんです。
もちろん、いきなり完璧な結果は出ません。でも、1歩ずつ“使える知見”が積み上がっていきます。
第3部:PoCで試してみる──スプレッドシートで始めるAutoML超実践ステップ
「試す」と言っても…何から始めれば?という方へ
「いやいや、GCPとかBigQueryとか出てくるともうムリです…」
そんな方、正直多いと思います。
でもご安心ください。
今回ご紹介するのは、「Googleスプレッドシート+Connected Sheets+AutoML Tables」を使った“ほぼクリックだけ”でできる流れです。
現場でPoC(試し使い)を回したい方は、まずこの流れだけ覚えておけば大丈夫です。
STEP 1|表を「AIが読み取れる形」に整える
いちばん大事なのはここです。
AutoMLに渡す表には、“ある一つの条件”があります。
✅ 目的変数(正解ラベル)が入っていること
- 次回来店が「あり/なし」
- 問い合わせの「契約につながった/つながらなかった」
- 売上が「前月より上/下」
この「結果」の列があることで、「この条件のときにどうなるか?」をAIが学習できるようになります。
✅ 変数(条件になる列)もできるだけ豊富に
例:美容業の表なら…
- 来店日 メニュー 担当者 単価 所要時間 来店間隔 次回来店
これらのデータが、全部「特徴量」として使われます。
👉 ポイントは、「最初から完璧な表を作ろうとしないこと」。
まずは ある範囲で試せるものから始める のが正解です。
STEP 2|Google Cloudの初期登録(無料)
- Googleアカウントがあれば誰でも開設できます
- 登録時に「$300分の無料クレジット」がもらえます(90日有効)
この範囲で、小規模データのPoCは余裕でまかなえます。
業務部門だけでこっそり試す…というのも、ここから可能です(笑)
STEP 3|Connected SheetsでスプレッドシートとBigQueryをつなぐ
「Connected Sheets」とは、Googleが提供する拡張機能で、
- スプレッドシートからBigQuery(データベース)と連携
- SQL不要で、Google表計算のまま集計・分析ができる
というものです。
「データベースが分からない」
「SQLとか無理」
そんな方でも、“いつもの表”からAI予測まで持っていけます。
STEP 4|Vertex AI のAutoML Tablesを使って学習させる
ここからが、いわゆる「AIモデルを作る」パート。
- Google Cloudの「Vertex AI」を開く
- 「AutoML Tables」→「新規データセット作成」
- BigQueryからさっきの表を指定
- 「目的変数」を選んで「学習スタート」
これで、特徴量設計、アルゴリズム選定、交差検証、精度評価まで──
全部、自動でやってくれます。
STEP 5|結果をスプレッドシートに戻して“使える形”に
AIモデルを作ったら、結果を現場で使えるように落とし込みます。
- スプレッドシートにスコア(たとえば「再来確率85%」)を出力
- 条件付き書式で「赤:高確率」「緑:低確率」など色分け
- 営業リストや来店促進のアプローチに使う
「この人、来そうだな」
「この案件、契約取れそう」
という“感覚”が、“数字”で裏づけられるようになります。
第4部:PoC後によく出る“つまずき”と、無料で試せるツール比較まとめ
PoCをやってみたけど…現場でよくある“壁”
PoCが無事完了しても、次にこんな壁が出てきます。
✅ 「で、これ…誰が見るの?」問題
精度は出た、グラフもきれい、スコアも見える──
でも結局、誰が見て、いつ判断に使うのか?が曖昧なまま…
これは「AI導入=成果が出る」と過信してしまうケースです。
👉 解決策は?
→ 最初から「活用シーン」を想定して始めること。
「この予測結果を、来週の営業会議で使う」と明言しておく。それだけでPoCの精度は跳ね上がります。
✅ 「すごいけど難しい」問題
「これはすごい。でも…この表、誰が回すの?」
AutoMLの結果は複雑になりがちです。
特に「特徴量の重要度」とか「AUC」とか出てくると、現場はパンクします(笑)
👉 解決策は?
→ “誰に説明できるか”を意識して、出力方法を整える。
条件付き書式、図解、スコア付き名簿など“業務に馴染む見せ方”を工夫することが重要です。
じゃあ、どのツールを使えばいいのか?(無料〜少額で始められるツール比較)
✅ Google Cloud AutoML(Vertex AI Tables)
- 特徴: 本格的な予測モデルをGUI操作だけで構築
- 価格: 登録時に$300分の無料枠/月数百円〜
- 向いている人: 「まず1つ本物を触ってみたい」人
✅ BigQuery + Connected Sheets
- 特徴: SQL不要で、スプレッドシートから集計・分析ができる
- 価格: 常時無料枠あり(1TB/月まで)
- 向いている人: 「表のまま分析したい」「まず整えたい」人
✅ AppSheet(Google製ノーコードアプリ)
- 特徴: スプレッドシートと連携した現場向け入力フォーム作成
- 価格: 無料枠あり/本格利用は月6ドル〜
- 向いている人: 「まず“データをためる仕組み”をつくりたい」人
✅ スプレッドシート単体でやるなら…
- Googleスプレッドシート+関数(FILTER/QUERYなど)
- GPTに貼り付けて“仮説出し”だけやってみる
→ これも立派なPoC。まずはここからでもOKです。
導入を続けるかどうかは、“予測精度”ではなく“使えるかどうか”
PoCで一番大事なのは「精度」じゃないんです。
「これは使えそう」「あの資料に混ぜられそう」「現場が納得しそう」──そう思えるかどうか。
中小企業では、精度90%の予測よりも、“行動に変わるヒント”のほうが価値があります。
第5部:まとめ──AutoMLは“完璧な答え”じゃなく“動けるヒント”
中小企業にとって、AIは“重装備”ではなく“作業着”
- 完璧な予測を出すことが目的ではない
- 精度99%でも、誰も見なければ意味がない
- 精度60%でも、「あ、これ動けるかも」があれば十分
私たち中小企業にとって、AIは「工場に導入する大型ロボット」じゃなく、「普段の作業をちょっと楽にする“手袋”みたいなもの」だと思うんです。
最初の一歩は“スプレッドシート1枚”から
「とりあえず30件、過去の案件を並べてみた」
「GPTに読ませて“何が見えそうか”相談してみた」
それだけで、もうAutoMLの入口に立ってます。
AUTOMLの始め方
✅ スタートのおすすめ順
- データを記録する:AppSheet、Googleフォームなどで「ためる」習慣をつくる
- 仮説を立てる:ChatGPTで「このデータから何が見えそう?」と相談
- 表を整える:スプレッドシートで「条件」と「結果」を並べる
- AutoMLにかける:Vertex AI Tablesで予測モデルを自動生成
- 業務に混ぜる:営業会議や販促施策に“予測スコア”を添えてみる
背中を押す言葉として、こんな話があります
ある中小企業の方が、AutoMLを使って「営業見込み案件のスコアリング」を始めたんですね。
最初は誰も見てなかった。でもある日、営業部長がこう言いました。
「これ、精度どうこうより“部下への声かけのきっかけ”になるわ」
…それを聞いたとき、私は思いました。
「あ、こういう“使い方”こそが、AIと共に働く未来だな」と。
最後に──“やってみる”からしか見えないものがある
AIを入れる理由も、始める手段も、きっと会社ごとに違います。
でも共通しているのは──
- 「見えなかったものが、少しずつ見えてくる」
- 「判断の勘が、数字で裏打ちされる」
- 「現場の迷いが、動ける材料に変わる」
…そんな“変化の始まり”が、AIそしてAutoMLにはあるということ。人間の最終判断を促す材料としてのAIの分析予測。AIを活用した直感、ですかね。
この記事が、誰かの背中を、ほんの少しでも押せたら嬉しいです。
“次の一歩”を一緒に考えたくなったら、いつでもご相談くださいね。










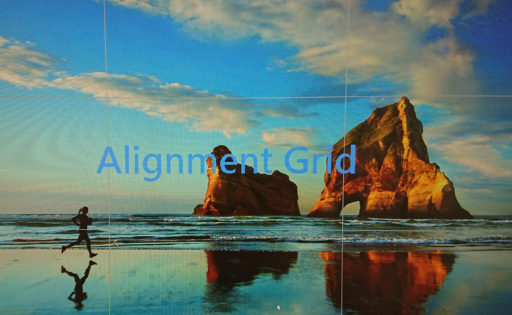





「そもそもAutoMLって何の略かも分かってなくて…」
「GPTで分析させときゃいいんじゃないの?」