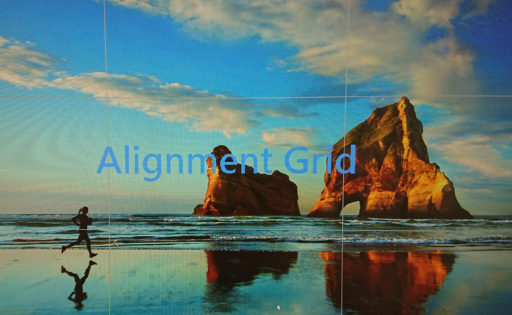こんにちは。投げっぱなしジャーマンは嫌ですが、ぶん投げOJTは嫌いではないです(その時は大変だけど成長度は高い)。株式会社セレンデック代表の楠本です。
最近、クライアント企業からこんな相談をよく受けます。
「教育、まったく追いついてないんです…」
この相談から始まった
- 教育にコストがかかる
- 教えても定着しない
- 育成した人が辞める
これは決して珍しい話ではありません。私たちセレンデック自身も、過去に「マニュアルを作っても読まれない」「OJTが回らない」「ベテランが属人的に抱えて疲弊する」といった、“教育が仕組み化されない苦しみ”を味わってきました。
そして外注研修やマニュアル整備に頼っても、結果は同じ。教育が「場当たり」であり続ける限り、組織は変わらないと実感しました。
ChatGPTだけでは足りない。「自社のやり方」を教えられない問題
よく「ChatGPTを導入してみましたが、結局使いこなせませんでした」という声を聞きます。
その背景には、汎用AIの特性があります。
- 一般論は得意でも、自社の“例外処理”や“空気感”は拾えない
- 言語化されていない“現場判断”がAIにはわからない
実際に、「とりあえずAIに聞いてダメだった」「じゃあ無理ですね」と思考停止する例が増えています。
でも本来、属人化していた知識こそAIに継承させたい情報のはず。つまり、一番教えたいことが、AIでは教えられない。 このジレンマこそ、教育におけるAI活用の最大の壁かもしれません。
自社ナレッジ × 生成AI = 教育内製化の新スタイル(RAG型AI活用)
そこで注目すべきが「RAG(Retrieval-Augmented Generation)」という考え方です。
これは、自社のナレッジデータをAIに連携し、検索ベースで文脈に即した回答を生成する仕組みです。たとえば、マニュアルや手順書、社内チャットの履歴などを読み込ませることで、「自社のやり方」を答えられるAIをつくる──そんなイメージです。
実際の構築ステップ(ざっくり簡略Ver):
- 社内マニュアル、手順書、FAQ、議事録をNotionやスプレッドシートに整理
- それらをRAG対応AI(ChatGPT・Claudeなど)に連携
- 社内用ボットとして試験運用し、QAを蓄積・自動学習化
こう聞くと…
「それ、なんか難しそうですね」
「エンジニアがいないと無理じゃないですか?」
…という声がよくあがります。
はい、正直に言うと“ゼロから内製”はかなりハードルが高いです。
でも実は、いまこの領域は急激に支援環境が整ってきています。
- 補助金・助成金の対象になるAI活用プログラム
- セレンデックのような外部パートナーがRAG構築まで伴走できる体制
- Notion/Googleスプレッドシートなど、普段使いツールを活用した“超低コスト運用”の仕組み
「なんか難しそう…」と感じた方へ
おひとりで悩むよりは、すでに経験している専門家にお任せしたほうが早いです。餅は餅屋です。
まずはお気軽にご連絡ください。
「人を育てる」から「育つ仕組みをつくる」へ──AIの本当の価値
教育というと、どうしても「誰が誰に教えるか」という発想になりがちです。
でもAIを活用することで、「教える行為」そのものが仕組みに変わります。
- 教える人が変わっても、ナレッジが残る
- 再現性が高まり、新人育成のハードルが下がる
- 現場で実践されるたびに、学びが蓄積されていく
これはまさに、「育つ仕組み」そのものです。
【現場あるある】私たちがハマった“3つの落とし穴”
1. AIに任せすぎて「思考しない新人」が育った(指示待ち人間化)
- すぐAIに聞いて「分かりませんでした」で終了
- AIごとの得意不得意を理解しないまま使う
- カスタマーサポートに聞けば済むようなこともAIで解決しようとする
これは完全に“AI信仰”による思考停止の状態です。
本来は、AIが出せなかったことこそ「なぜ出ないのか」「どう表現すればいいか」を考えるべき瞬間。でも、その“思考の余白”をすっ飛ばしてしまう──教育とは逆方向に進んでしまうんです。
2. 精度重視で時間をかけすぎて現場に浸透しなかった
- 完璧なFAQを作ろうと時間ばかりかかる
- 現場の変化は早く、「動かしながら改善」しないとすぐに古くなる
初期フェーズは“70点でリリース、回しながら育てる”ぐらいがちょうど良い
3. 担当者だけがハマって孤立。全社共有の流れがなかった
- 担当者だけが熱中し、周囲は「また新しいツールね…」と冷めた反応
- 情報共有されないまま属人化が再発
教育もAI活用も“みんなで育てるもの”という文化づくりが必要だった
教育とは“問いを生む力”を育てること──AIがくれた静かな気づき
私自身、生成AIを使っていて「これ、教育そのものだな」と感じることが増えています。
たとえば、あるスタッフが「これってAIに聞いても出てこないですよね」と言ってきたとき──
私は、こう返しました。
「うん。でも、その“出てこなさ”に気づいたのが、もう学びなんだよ。まずはポジティブに捉える(本田圭佑の真似をするじゅんいちダビッドソン風に)」
正解が出なかった。でも、その時に「なぜ出ない?」「どんな聞き方をすれば?」と考える時間が生まれる。
これこそ、“問いを育てる時間”です。
教育とは、答えを教えることではなく、「問いを持つ力を育てること」。
生成AIは、その“問いの余白”をつくるパートナーになり得る。──そんな静かな確信があります。
まとめ:AIは“教育の外注”をやめるためのパートナー
生成AIは、ただの便利ツールではありません。
- 教える側を楽にする
- 教わる側が考える
- 学びが組織に溜まる
この三拍子がそろって初めて、教育は“仕組み”になります。
属人化から脱却し、「育つ文化」をAIで根づかせる。これが私たちの目指す「教育の再設計」です。
AIの登場によって教育の方法も根本的に変わってきました。AI時代、一緒に頑張っていきましょう!
ご案内
- 個人向け:AI時代の“考える力”を育てる
『AI Webディレクター養成講座』- ChatGPTやGeminiなどを活用した、ゼロから始めるAI仕事術
- Webの基本技術、ヒアリング・構成・提案・ライティング・AI活用の“ディレクション5技能”を実務に落とし込む
- Web初心者・未経験者でも、「考える力」と「伝える力」を体系的に学べる講座です。0からAIwebディレクターとして活躍できるまでをサポートします
- 法人向け:AI導入から内製化までを設計
『AI・DX戦略構築講座(法人研修プラン)』- 現場で「なぜ進まないのか」を構造的に分析
- 部署別ヒアリングから始める“内製化の第一歩”
- 最新AIツールの活用例と、現場に定着させる教育設計をワーク形式で支援