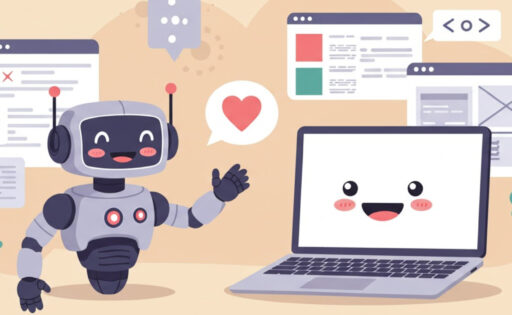解説YouTube動画はこちら 仕事が取れないWEBデザイナーの現実
「Webデザインを勉強して、さあフリーランスのwebデザイナーとして頑張るぞ!! だけど、、なぜ案件が来ないのか?」
こんにちは、Webデザインでキラキラ吉良上野介、株式会社セレンデック代表の楠本です。
ポートフォリオを一生懸命作った。
デザインも整えたし、バナーやLPの制作実績も並べた。
「これなら大丈夫だろう」と思った──でも、なぜか応募しても返事がない。
そんな経験、ありませんか?
これは、私たちが現場で何百人もの初心者・フリーランスWebデザイナーを見てきた中で、最も多くの人がつまずいているポイントです。
そして、結論から言えば──
「作ったものを“見せる”」だけでは、案件にはつながらない
ということ。
本記事では、案件が取れない理由と構造を、現場目線で解説していきます。
ポートフォリオが“成果”に繋がらない3つの根本原因
①「見せる順番」と「伝える意図」がない
多くの初心者Webデザイナーのポートフォリオは、“作品集”としては成立しています。
でも、そこに「なぜこれを入れたのか?」「誰に何を伝えたいのか?」が抜けていることがほとんどです。
たとえば、バナー3つ、LP2本、イラスト5枚が並んでいたとします。
でも、発注者が見ているのは“量”や“デザイン性”だけではありません。
この人は「どんな思考で」「どんな目的で」「どんな成果を生むものを作ったのか?」を見ています。
その「なぜ?どうやって?」が語られていないポートフォリオは、
どれだけ綺麗でも、“発注される理由”にはなりません。
② 「提案力」が見えない
ポートフォリオは“作品紹介”ではなく“企画書”であるべきです。
- なぜこの構成にしたのか?
- 誰向けの商品で、どこを訴求しようとしたのか?
- どんな改善ポイントを意識したのか?
これらを言語化して添えることで、
「この人は、ちゃんと“考えて作れる人だな”」と評価されます。
作業者ではなく“提案できる人”のポジションに上がるには、
この構造が不可欠です。
特に、駆け出しのフリーランスや副業デザイナーは、
「ただ作れる」だけでは差別化が難しい現実があります。
だからこそ、“まとめて伝える力”が武器になるのです。
③ 「稼げる構造」がそもそもズレている
ポートフォリオは「作品を見せるため」ではなく、
「案件を生み出すためのプレゼン資料」です。
- 高単価案件が求めているのは「ビジュアル」ではなく「成果」
- 企業が欲しいのは「作れる人」より「動かせる人」
- 今はAIでも制作できる時代だからこそ“選ばれる理由”が必要
この構造を理解していないと、
どれだけポートフォリオを作り込んでも、
“選ばれない人”のまま止まってしまいます。
増える「テンプレートポートフォリオ」の問題点
最近は、ポートフォリオ専用のテンプレートもたくさん出回っています。
NotionやSTUDIO、Webflow、あるいはFigma用など──
デザイン済みの土台に作品を流し込めば、それっぽく見える。
正直、便利です。AIもドンドン進化しています。
私たちもテンプレートを否定はしません。
でも…現場でこんな話がよく出ます。
「これ、本当に自分で作ったんですか?」
実際、まったく同じ構成・同じ配色・同じ順番のポートフォリオを、複数の応募者が提出してくることも珍しくありません。
テンプレの存在を知っている人から見れば、
「これ、テンプレに画像流し込んだだけだよね?」と一瞬でバレます。
しかも、テンプレを使っていながら、
それを“あたかも自作かのように見せている”と、逆に信頼を損ないます。
本当に0から作ったのか?
あなたの言葉で説明できるのか?
それは、あなたの実力を証明できる資料になっているか?
──テンプレの“良さ”と“危うさ”を、どう設計で補うか。
それこそが問われているのです。
現場で選ばれるポートフォリオに共通する“5つの設計視点”
- 「構成=ロジック」が伝わるようにする
単に“並べる”のではなく、“選んで・並べて・説明する”。この順番で「考えた形跡」が見えるポートフォリオは、制作力よりも「設計力」が伝わります。 - 「誰向けに何を作ったか」が明示されている
架空案件でも構いません。重要なのは、「誰のために・何を・なぜ作ったか?」が言葉になっていること。これがあると一気に“仕事を任せたくなる人”になります。 - 改善提案・効果測定」への意識がある
提案職として評価されるには、「ビジュアル」だけでなく「課題と改善」を語れる必要があります。ABテスト、ヒートマップ、GA分析の視点が入っていると、評価は跳ね上がります。 - 「あなたの言葉」で説明されている
他人の表現を借りず、自分の言葉で語る。少し荒くても、拙くても、自分で考えた表現のほうが強いです。「この人は本当にこの仕事をしてきたんだ」と感じられるからです。 - 「次の提案」まで書かれている
「もしこのLPを改善するなら?」
「このバナーの別パターンは?」
といった“次の一手”が書かれていると、もうそれは“ディレクター的視点”です。
作るだけでなく、動かす・伸ばす人としての評価につながります。
ポートフォリオは“まとめる力”を証明するツール
デザインやコーディングができる人は、正直たくさんいます。
でも、「なぜこれをこうしたのか」を言語化し、構造としてまとめられる人は、その中でも一握りです。
ポートフォリオは、単なる“作品集”ではありません。
あなたの“設計力・思考力・提案力”を示す、ビジネスツールです。
そして今、Webディレクターという仕事が求められているのは、
まさにこの“まとめる力”が足りていないからです。
「私は作れる。でも、それを活かしきれていない」
そう感じたことがあるなら、ぜひ一度、AI × Webディレクターというキャリア設計をのぞいてみてください。
無料セミナー開催中|
「仕事につながるポートフォリオ設計法」
- 現場で“選ばれる人”のポートフォリオ構成とは?
- AIを使った構成案作成・改善フローを実演
- 無料で使えるフレームテンプレート配布中
LINE登録 or セミナー申込で、無料PDF特典もお渡ししています。
あなたのスキルや経験を、“作る側”から“動かす側”へと進化させる──
そんなキャリアをAIと一緒にデザインしてみませんか?