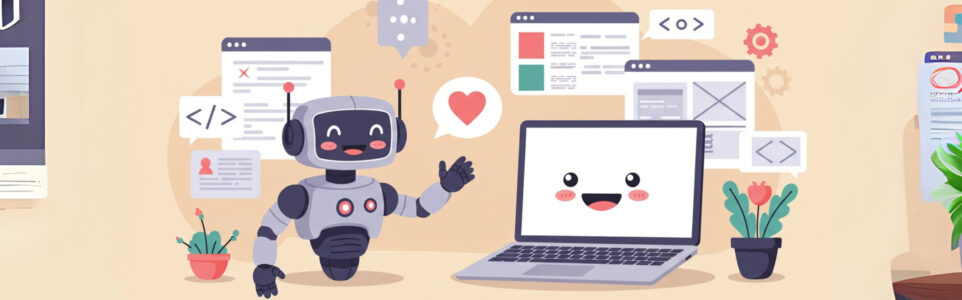こんにちは。AIとWeb制作は相性が良すぎて、もうこれは(AI)愛しあってるなと確信している、株式会社セレンデック代表の楠本です。
最近、Web制作の現場で「AIがここまでやるのか……」と、驚きの連続なんです。
実際、2023年以降、社内でAIを本格的に導入し始めてから、「業務の質」と「スピード」の両立が、現実のものとして見えてきました。
これ、実は今まで一番頭を悩ませてきた部分なんですよね。効率化しようとすれば質が落ちる。質を上げようとすれば時間がかかる。このジレンマに、多くのWeb制作者が直面していたのではないでしょうか?
でも、AIの進化が、この難しい問いに対する明確な答えの一部を示し始めているんです。
今回は、私自身の経験も踏まえながら、「AI×Web制作」の変化を、5つの視点から深掘りして解説します。AIによるWeb制作の革新が、いかにして業務効率と品質を同時に高める新しいアプローチを提供しているのか。
ただの効率化に留まらず、「働き方」「技術習得の考え方」「AIとのこれからの付き合い方」まで含めて、未来を見据えた視点でお届けできればと思います。
※本記事の情報は2025年7月25日現在の内容です。AIの進化は目覚ましいものがありますので、今後の変化にご注意ください。ただし、本質的な考え方については今後も変わらず参考にしていただける内容です。
Web制作におけるAI革命:2025年の潮流を読む
まず、今のWeb制作業界の背景からお話ししましょう。このセクションでは、Web制作におけるAI活用の具体的な事例と、それが私たちの仕事にどのような影響を与えているかを探ります。正直、変化のスピードには驚くばかりです。
2022年〜2025年、ChatGPTやMidjourneyの登場を皮切りに、AIの進化が”日常レベル”にまで降りてきました。まるでSFの世界が、目の前に現れたような感覚ですよね。
そして今年、2025年にはさらに大きな転換点を迎えています。特に注目すべきは、以下の動きです。
- Microsoft Build 2025では、「AIエージェントの爆発的進化」が報告され、Web制作もまさに“エージェント型Web”の時代に突入しました。
- あのFigmaが「Figma Make / Sites」を正式公開し、テキスト入力だけでWebレイアウトやアプリ設計が可能になったんです。昔からBINDやWIXなどのノーコードツールはありましたが、バイブコーディングの流れはさらに強まるんでしょうね・・
- ReplitのAgent v2 や CursorのBugbot など、AIがコードを書くだけでなく、「品質まで担保する」方向へ進化しています。
- さらに、AlibabaのQwen3-Coder や MistralのDevstral など、高性能かつオープンなAIコード生成モデルが次々と登場し、開発現場に大きな変化をもたらしています。
もう、AIは「もしかしたら使えるかも?」というフェーズでは全くありません。
もはや“どう使うか”が、Web制作者としての「差」になる時代に突入しているんです。
この潮流を理解し、適切に活用することが、今後のWeb制作において非常に重要となるでしょう。AIの導入は、単なるツールの追加というよりも、ワークフロー全体の変革を意味します。これまで時間を要していた反復作業や、複雑な分析がAIによって効率化されることで、私たちはより創造的で戦略的な業務に集中できるようになります。新しい技術への適応が、これからのビジネスの成長と競争力向上に直結するのは間違いないと、私自身も日々実感しているところです。
本質は変わらない。ただ“そこに至る過程”が激変している
「AIに仕事が奪われるのでは?」──よく、そんな不安の声を耳にします。でも、実際の現場に立ってみると、その感覚とは真逆だと感じています。
私たち人間が担うべき役割は、今も昔も、そしてこれからも変わらないんです。具体的には、この3つです。
- クライアントの本質的な課題を聞き出す力
- 情報を深く咀嚼し、具体的な設計に落とし込む力
- 最終的な責任をもって、最適な“選択”をする判断力
変わったのは、その手前──つまり“準備と組立”のパートなんです。ここですね、AIが劇的な変化をもたらしたのは。
AIがこのプロセスに入り込むことで、Web制作の半分以上が驚くほど軽くなります。私たち人間は、これまで大変だった準備作業から解放され、より高度な意思決定や戦略立案といった、本来集中すべき業務に時間を割けるようになるんです。まさにAIと人間の協業が、これからのWeb制作者の役割を再定義し、新しい価値を創造することを可能にしているんです。
この変化を前向きに捉え、AIとの協業を通じて、これまでの限界を超えたクリエイティブな成果を目指すことは、私たちにとって大きなチャンスだと考えています。
例えるなら、「AIは、めちゃくちゃ優秀な設計助手。でも、プロジェクト全体の設計思想までは持っていません」
そんなイメージが近いでしょうか。私たちはこのAIを使いこなし、その可能性を最大限に引き出すことで、これまで以上の質の高いWeb制作を実現できる。そう信じています。
AIでWeb制作を革新する5つの方法(2025年最新)
⚠️ 補足:ここでご紹介する最新ツールや手法は、2025年7月現在のトレンドをもとにしています。AIの進化はまさに“指数関数的”に進んでおり、今後も次々と新たなサービスや技術が登場するでしょう。
そのため、これらの情報は常にアップデートが必要です。まさに「追いかけるのが大変!」と感じる方もいるかもしれません。
ですが、だからといって「流行を追い続けるだけ」では、Web制作の本質を見失ってしまいます。
AIがどんなに進化しても変わらない価値──それは、「ユーザーの本質的な課題を見抜く力」「目的を設計する力」「そして、最終判断に責任を持つこと」です。
つまり、“変わらないものを軸に、変化する技術を賢く活用する”という姿勢こそが、これからのWeb制作者にとって最も重要なのではないかと、私自身は考えています。
では、具体的にWeb制作のどんな部分にAIを取り入れられるのか?私の現場で“実際に効果を実感できている”領域として、以下の5つが挙げられます。
1. デザインの自動化:Figma Makeでレイアウトもプロトタイプも一発生成
2025年7月にFigmaが正式公開した「Make」は、プロンプト入力だけで構成・配色・モジュール提案まで可能にしてくれました。これぞまさに、待望のAIデザインツールの進化形と言えるでしょう。
これにより、私たちはゼロからデザインを考える時間が劇的に減り、デザイナーは「数ある提案の中から最適なものを選ぶ」という創造的な作業に、より集中できるようになります。
また、今後さらに増えると予想しているのが「既存テンプレートの再活用」です。
もちろん、完全オリジナルで唯一無二なデザインは、引き続き超一流のWebデザイナーが活躍する領域であることに変わりはありません。
しかし、すべてのWebサイトが“スーパークリエイティブ”である必要はありませんし、実務上は既存のテンプレートやAIが生成した提案をうまく活用するほうが、時間とコストを考えても合理的な場面は非常に多くあります。これによって、より多くのクライアントのニーズに、迅速かつ高品質に応えられるようになるんです。
──このあたり、語り出すと長くなるので、また別の記事でじっくり深掘りさせてくださいね(笑)。
特にデザインは、皆さん大好きなテーマですからね。
2. コード生成:Qwen3-CoderやDevstralが圧倒的高精度
AlibabaのQwen3-CoderやMistralのDevstralといった最新モデルが、Web系のコード生成で特に優れた精度を発揮しているのをご存知でしょうか?私も使ってみて、その正確さには目を見張るものがありました。
ReplitのAgent v2やCursorの「vibe coding」といったツールによって、今や自然言語からのコーディングも一般化してきました。まるで「こんなサイトが欲しい」と話すだけで、コードが生成されていくような感覚です。
これにより、開発者はより高速に、そして正確にコードを生成できるようになり、開発サイクルの短縮と品質向上に大きく貢献します。結果として、Web開発の生産性は飛躍的に高まり、私たちの働き方も大きく変わっていくでしょう。
手作業でのコーディングに費やしていた時間が削減されることで、より複雑なロジックの検討や、ユーザー体験の細かなチューニングに集中できるようになるのは、本当に素晴らしいことですよね。
3. パフォーマンス最適化:AIが高速化ポイントを指摘+コード出力
Webサイトの表示速度って、ユーザー体験だけでなく、SEOにとっても非常に重要ですよね。従来のLighthouseのような診断ツールに加え、2025年現在ではAIが実際のサイト構造やトラフィックデータを解析し、「ここを改善すればもっと速くなる!」といった最適化ポイントを具体的に提案するケースが増えています。
たとえば、Vercel+Next.js環境ではAIがJavaScriptのバンドル分割や画像最適化の設定を自動で修正提案してくれる仕組みまで登場しています。これには私も感動しましたね。
こうしたAIの取り組みにより、ページ読み込み速度やSEOスコアが改善し、結果としてサイトからの離脱率の低下にもつながるという、まさに良いことずくめの効果が得られています。
2025年には、PWA構成やヘッドレスCMS(例:Contentful、Strapi)と連携することで、AIによる構成最適化が“現実の選択肢”として、すでに多くのプロジェクトで組み込まれています。これにより、Webサイトのパフォーマンスを最大化し、ユーザーエクスペリエンスも大幅に向上させることが可能となります。AIが裏で支えることで、私たちは複雑な最適化作業に時間を取られることなく、本来の業務に集中できるようになった、というわけです。
4. パーソナライズ:エージェント型のUI提案が進化
Webサイトを訪れる人それぞれに最適な情報やレイアウトを見せる「パーソナライズ」は、もはや夢物語ではありません。Microsoft CopilotやGoogle GeminiなどのAIが、ユーザーの過去の閲覧履歴やサイト内行動データをもとに、ページレイアウトやCTA(Call To Action)の位置・コピーを動的に変化させる技術が、現実に多くのサイトで使われ始めています。
たとえば、ECサイトでは、再訪ユーザーには「カートに残っている商品」や「過去に見た類似商品」を冒頭に表示するなど、再訪率・CV(コンバージョン)率アップに直結する仕組みが整っています。
LPO(ランディングページ最適化)にもAIが導入され、OptimizelyやMutinyといったツールでは、業種別・ペルソナ別に最適な構成を自動提案してくれるケースも出てきています。これには、私自身も「ここまでやるのか!」と驚かされました。
「パーソナライズは未来の話」と捉えられていた時代はもう終わりました。現在では既に成果が出始めている実用フェーズに突入しているんです。これにより、個々のユーザーに最適化された体験を提供し、エンゲージメントとコンバージョン率の向上を同時に実現できます。AIがユーザーの心をつかむための強力な武器になってくれるわけです。
5. テスト自動化:CursorのBugbotでコードレビューとUIテストを統合
Webサイトの品質担保は非常に重要な工程ですが、テストには膨大な時間と労力がかかりますよね。しかし、今やAIがコードのバグを指摘するだけでなく、その後の再発防止策の提案やテストケースの自動生成までこなすようになっています。これは、まさにAIテスト自動化の最前線です。
これにより、品質担保の領域が大きく変わってきています。開発プロセス全体を通じて、より早期に問題を特定し、修正することが可能になるため、最終的なWebサービスの信頼性が飛躍的に向上します。以前は手作業で多くの時間とコストがかかっていたテスト工程が、AIの力で効率化され、私たちはより本質的な改善に集中できるようになるのです。これは、開発者にとって本当に心強いアシスタントだと言えるでしょう。
※それぞれの詳細は、個別記事で深掘りしています。気になる項目があれば、ぜひリンクからどうぞ!
セレンデックの現場でも実践中:「ちょっとやってみたら、案外イケた」
私自身、もともとAIに対しては「面白そうだから、まずは試してみよう」という、いわば好奇心先行型の人間なんです。
2024年春頃から社内で「AIコード生成」を本格的に試し始めたのですが、正直なところ、その効果には驚かされましたね。
- 以前は2時間かかっていたパーツ設計が、たったの15分で完了。
- しかも、その後の手直しの時間を含めても、半日かかっていた作業が1時間に短縮されたんです。
現在では、Figma MakeやCursor、そして私が個人的に「これはすごい!」と感動すら覚えたReplitも積極的に活用しています(笑)。
さらに、コード生成ではV0やBLOTといったツールも注目していますし、アイデア出しや準備段階ではChatGPTやClaudeもほぼ毎回使うようになりました。こうしたAIの組み合わせによって、まさに“本質的な思考”にリソースを割けるようになってきているんです。これは、業務効率化だけでなく、より質の高いアウトプットを生み出す上で不可欠な変化だと強く感じています。まさに当社のAI導入事例として、この実践が今後のWeb制作の生産性向上に大きく貢献することを日頃から実感しています。
正直な話、使ってみた有料ツールの多くは、裏側でChatGPTのAPIを使っているな、という印象もありました(まあ、当然といえば当然なのですが)。
とはいえ、簡単なものであればどのサービスでも十分に使えるレベルですし、最終的には自分の使いやすさやコスト感に応じて選んでいくのが現実的だと思います。
あとは、やっぱり「どうしようかな…」と迷うより、「とりあえず試してみる」ことが一番の近道かもしれませんね。私自身もそうやって一歩を踏み出しましたから。
これからWeb制作者に求められるのは「AIを使いこなす力」
AIは、私たちWeb制作者にとって、決してライバルではありません。むしろ、最高のアシスタントになってくれます。
でも、その“優秀な助手”をどう使いこなすかで、最終的に生み出される成果はまったく変わってくるのが面白いところです。
今後、Web制作者に求められる力は、以下の点に集約されると私は考えています。
- 数あるAIツールの中から、最適なものを選ぶ「目利き力」
- AIが出力した結果を、鵜呑みにせず自分で判断できる「見極め力」
- そして、ツールに依存するのではなく、自分の頭で本質的な設計ができる「バランス感覚」
これらは、まさにAI時代における“思考する技術”とも言えるかもしれません。AIを活用することで、これまで以上に効率的かつ質の高い制作が可能となり、結果としてWeb制作者としての市場価値を大きく高めることができるでしょう。変化を恐れず、積極的にAIを取り入れ、それを使いこなす姿勢こそが、これからの成功の鍵を握っていると私は確信しています。
まとめ:AIと共に、Web制作の未来を味方につける
Web制作の本質──それはいつの時代も、「ユーザーの課題を、Webの力でどう解決するか」という一点に尽きます。
この本質は、どんなにAIが進化したとしても、変わることはありません。
しかし、その“届け方”“作り方”“伝え方”は、AIと共にどんどん進化しています。これは、私たちWeb制作者にとって、まさに追い風ですよね。
変化を怖がるのではなく、まずは一歩踏み出して、試してみる。
そして、実際にやってみて「あ、これは本質的だな」「これは私たちの仕事に役立つぞ」と感じたら、積極的に取り入れていく。
未来は、“試してみた人”から変わっていくと、私自身も日々感じ、信じています。この大きな変化の波を捉え、AIを最大限に活用することで、ぜひWeb制作の新たな可能性を一緒に切り開いていきましょう。
よくある質問(FAQ)
Q1. AIに任せると、スキルが育たないのでは?
→ 基本構造はAIに任せつつ、最終的な判断や改善は人間が担当することで、むしろこれまで見えなかった部分への理解が深まり、スキルアップにつながりますよ。
Q2. 無料ツールだけでも十分使えますか?
→ 一部の簡単な作業であれば可能ですが、商用レベルの本格的なWeb制作で活用するには、やはり有料ツールやAPI連携が必要になるケースが多いですね。
Q3. 初心者でも使いこなせますか?
→ むしろ初心者の方こそ、AIの提案を通じて効率よく、実践的に学べる側面があります。私も含め、多くの人がAIをきっかけにスキルアップしていますよ。
Q4. AIが出力するコードって、安全ですか?
→ 基本的なセキュリティには対応していますが、最終的なリリース前には必ず人間がコードのレビューを行い、安全性を確認する必要があります。AIも万能ではないので、最終チェックは必須です。
Q5. 自分に合うAIツールの選び方がわかりません
→ たくさんあって迷いますよね。各カテゴリのおすすめツールを解説した小記事も公開していますので、ぜひそちらを参考にしてみてください。
これらの記事では、それぞれのテーマについて私が現場で得た知見や具体的な事例を交えながら、さらに深く掘り下げています。AIをWeb制作に活用するための具体的なステップや、最新ツールの選び方についても詳しく解説していますので、ぜひご参考にしてください。きっと、皆さんの「やってみよう!」という気持ちを後押しできる実践的なノウハウが詰まっているはずです。
AIを実務で活用するための講座
「じゃあ、どうやってその力を身につけるのか?」
「現場で、AIをどんな風に使えばいいのか?」
そうした問いにお応えする形で、AIを実務で活用するための2つの講座を運営しています。
🎓 AIディレクター育成講座(主に個人向け)
「言語化」「問いの設計」「アウトプット改善力」を体系的に学べるオンライン講座。未経験からでも“使いこなせる人”になるための実践ノウハウを凝縮。社内のWeb運営の内製化のためのスタッフ教育にも使えます。助成金対応しています。
セレンデックではAIウェブディレクター育成講座を開催しています。ご興味ある方は是非ご参加ください。体験会、説明会も実施しています。
👉 AI Webディレクター養成講座はこちら
🏢 AIDX法人講座(企業研修向け)
中小企業の現場で成果を出すための、AI内製化&チーム導入支援プログラム。実際の業務課題を教材に、チーム単位でAI活用を浸透させていきます。
ぜひ、私たちと一緒に「試してみる」ことから始めていきましょう。