「AIは変な答えしか出ない」は本当か?──“使い方がうまくないあれ”だけかもしれません(笑)
はじめに──「頑張ればなんとかなる」は美徳か幻想か
こんにちは。真夏でも水を飲まずにうさぎ跳びをして、理不尽さに打ち勝つメンタルを鍛えている男、株式会社セレンデック代表の楠本です。
先日、ある経営者仲間との雑談で、こんな話が出ました。
……いや、それ、“使い方があかんのやで”と、思わずツッコミたくなりました(笑)。
そりゃ「AIさんこんにちは。営業戦略教えて」って聞いたら、フワッとした答えしか返ってきませんよ(笑)。
でも、気持ちは分かるんです。僕も最初はChatGPTを触って、「なんやこれ、ふわっとしてて使えんな」と思った時期がありました。
でもそこから、“ちゃんと向き合って、使い方を工夫する”ことで、見える景色が一変したんです。
この記事では、AI時代における「努力」の再定義と、仕事に対する“価値観の転換”について、一緒に考えてみたいと思います。
「努力は報われる」という前提が、音を立てて崩れ始めている
これまでのビジネス社会では、「人より頑張る」「根性で乗り切る」という姿勢が美徳とされてきました。
実際、僕自身も若い頃は「寝ずに働けば勝てる」と信じてましたし、深夜まで資料をつくり、休日も現場に出てました。
でも、AIの登場で、その“がむしゃらな努力”が、報われにくくなってきている。
なぜか?
- AIは24時間、疲れ知らずで動ける
- 1秒で何万文字ものテキストを生成できる
- 情報収集や整理が人間の10倍以上速い
つまり、「頑張るだけの人間」は、量でAIに勝てない時代に突入したんです。この認識は、多くの人がまだ十分に持てていないかもしれません。
しかし、この冷徹な事実は、今後のキャリアや働き方を考える上で避けて通れないテーマです。私たちは、AIが持つ圧倒的な処理能力や効率性に対抗するのではなく、いかにしてAIと協調し、人間独自の価値を創造していくかを真剣に考える必要があります。
量的な努力だけでは通用しない時代が、すでに始まっているのです。
AIに勝てない領域とは何か──ホワイトカラーの“逆風”と“分岐点”
ちょっと残酷なことを言いますが、
“作業系ホワイトカラー”の仕事って、どんどんAIに置き換えられていきます。
例えば、以下のような業務です。
- 文章作成(定型文、議事録)
- 情報収集、リサーチ
- 企画のアイデア出し
- 表やグラフの自動生成
これらを「人がやっていた理由」は、「手間がかかるから」だったんですよね。
しかし、AIはこれらの作業を驚くほどの速さと正確さで処理できます。言い換えれば、AIにとってこれらは「得意分野」であり、人間が時間をかけて行う必要がなくなってしまったのです。
この変化は、特にルーチンワークに多くの時間を費やしてきたホワイトカラー層にとって大きな転換点となります。これまでの「頑張れば通用する」という前提は崩れ去り、「工夫しないと通用しない」時代へとシフトしました。この認識を持たずに、ひたすら努力を続けても、報われにくくなっていく。
少し厳しい話かもしれませんが、これは冷静な“現実”です。
求人動向に見る、現場仕事とホワイトカラーの“逆転現象”
とはいえ、あまり露骨に「ホワイトカラーは厳しい」と言うと、違和感を持たれる方もいますよね。なので、少し客観的なデータを紹介させてください。
たとえば、2025年までに日本では非デスクワーク(清掃・施設管理・建設・介護など)で最大800万人以上の人手不足が予測されています(出典:ザイマックス不動産総研)。
さらに、米国の労働市場ではホワイトカラー職の求人が鈍化し、逆に配送・介護・建設などの「現場系求人」に人気が集まる現象が顕著になってきました。
実際、若年層の中には「AIに奪われにくい職業」として、肉体労働や手に職系の仕事に就く傾向も強まっています。現場側の求人倍率は高止まりしている一方、ホワイトカラーの応募過多による“買い手市場化”も進行中です。
そしてもうひとつ、見逃せないのが「都内現場系の時給の高騰」です。
例えば、都心の「まいばすけっと」では、オープニング時に時給2,150円という破格の求人を出しているケースもあります。飲食チェーンでも、ホールスタッフで深夜1,750円前後が当たり前になってきました。
つまり、
現場=低賃金という図式は、すでに過去のものになりつつある
のです。
この現象は、「AIに置き換えにくい、リアルな対人・肉体労働」への社会的評価の裏返しとも言えます。
対人業務や五感を使う仕事の価値が上がっている
こうした潮流の中で再評価されているのが、
「肉体労働」や「対人業務」
なんです。
- 高齢者との会話や介護現場のケア
- 美容師、整体師、調理師などの手業
- 飲食店、物流、小売などの対面対応
これらは、“AIには真似できないリアル”を提供できる仕事。求人データでも、地域を支える非リモート業務は人材不足と賃金上昇が進み、むしろ「現場の方が評価される」時代が始まっています。
このような職種は、人間特有の感性やコミュニケーション能力を必要とし、AIが代替することが難しい領域です。
例えば、介護現場での心のこもったケアや、美容師が顧客の要望を汲み取りながら行う施術は、単なる作業ではなく、人間にしか提供できない付加価値を生み出しています。
このように、人間ならではの仕事の価値が見直され、社会全体の価値観が大きくシフトしているのです。
「AIなんて無料で十分」と思っている方へ──課金の本質
最近いろんな企業さんと話していて、気になるのが
「AIは無料の範囲で使ってるから十分」
という声。
でも、はっきり言います。
「無料=学びの壁が低い」反面、「成果も限られる」んです。
ここで少し、現実的な数字で考えてみましょう。
あなたの時給はいくらですか?
仮に年収1,200万円の経営者で、月100時間稼働とした場合──
時給は12,000円です。
そのあなたが、無料AIを自己流で試行錯誤して1日2時間余計に時間を使っていたとしたら?
→ 12,000円 × 2時間 × 20営業日 = 48万円/月の“目に見えない損失”です。
しかもこれは“無駄な試行錯誤に払っている”と考えると、かなり勿体ない。
一方で、ChatGPTやClaudeの有料版(月2,000〜3,000円)を導入すれば、プロンプトテンプレートの活用や自動化の導線も含め、月40〜50時間の業務圧縮も十分可能です。
月3,000円で、年収1,000万円レベルの「AI秘書」が24時間待機してくれる世界。
これ、どう考えても「使わない方が損」ですよね?(笑)
続きのパート(“工夫する努力”こそが、これからの競争優位になる 以降)もすぐにお届けします。
以下は続きを含む第2部です。
“工夫する努力”こそが、これからの競争優位になる
「じゃあ、努力って無駄なのか?」
──そんなことはありません。
大事なのは、
「工夫する努力」
つまり、
- AIを“どう使うか”を考える力
- 組み合わせて成果を出すセンス
- 周囲を巻き込むコミュニケーション力
こういった“創造的な努力”は、ますます価値が上がると思っています。これらの力は、AIがどれだけ進化しても人間が優位性を保てる領域です。
単純な作業はAIに任せ、人間はより高度な思考や創造性を要する仕事に集中できるようになります。
このシフトは、決して人間が仕事を奪われるということではなく、人間がより人間らしい仕事に時間を費やせるようになるというポジティブな側面を持っています。
一方で、「言われたことを言われた通りやる」だけの仕事は、AIにも、ロボットにも、置き換えられてしまう運命にあります。だから、僕らホワイトカラーも、“ラクをする”ためじゃなく、
「もっと人間らしく働く」ために、AIと向き合うべきなんです。
よくある質問(FAQ)
- Q1. AIを導入すると、人件費削減ばかりが目的になりますか?
A. いいえ、人間らしい仕事に集中するための「再配分」が本質です。 - Q2. 無料のAIでも成果を出すことはできますか?
A. 可能ですが、学習コストや手戻りが増えがちです。有料版との比較が重要です。 - Q3. AI活用に向いていない職種もありますか?
A. 対面重視や即応性が求められる現場は、AIとの“共存”がカギとなります。 - Q4. ChatGPTやClaudeの違いは何ですか?
A. GPTは文章生成に強く、Claudeは構造的な文書作成に向いています。目的に応じて使い分けが重要です。 - Q5. 中小企業でもAI導入は現実的に可能ですか?
A. はい、むしろ中小企業こそ“小さく始めて成果を出せる”AI活用法があります。
セレンデックのサービス
セレンデックでは「AIウェブディレクター育成講座」に加え、法人向けのDX・AI講座も展開しています。チーム導入・業務改善・社員教育まで、御社に最適な活用法をご提案します。
個人向け:AI Webディレクター養成講座はこちら
法人向け:DX・AI講座のご相談はこちら
最後に──“小さな違和感”を、次の行動につなげる
採用難が続く今の時代、
「いかにAIやITを活用して、少人数でも業務が回る仕組みを構築するか」
これは現場任せの課題ではなく、経営者にとっての“重要な責任”でもあります。ただ人数を増やすのではなく、知恵とテクノロジーで乗り切るための視点と準備が、これからの組織には求められていきます。
少子高齢化で、これから若者の採用がますます困難になることは確定しているわけですからね。若者に限らず人口統計として人手不足は目に見えてますからね。
少しでも今日もを持った方は遠慮なく、お気軽にご相談ください。一緒に頑張っていきましょう。










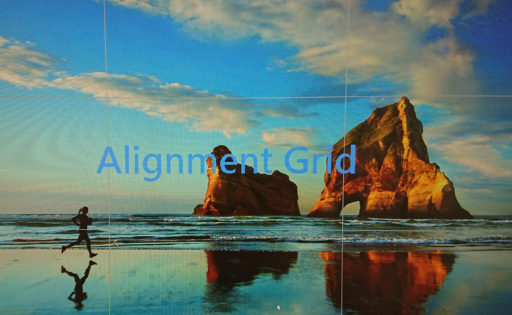





「いやー、AIって言っても、結局変な答えしか返ってこないでしょ?全然使えんよ」